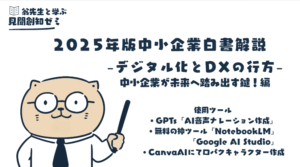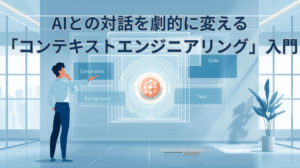近年、私たちの生活やビジネスを取り巻くデジタル技術の進化は目覚ましく、特に「生成AI(人工知能)」の話題を耳にしない日はないと言っても過言ではありません。人間が入力した情報(プロンプト)をもとに、文章や画像、音声などを自動で作り出すこの技術は、すでに世界の多くの国々で日常的に活用され、教育、医療、ビジネスといった多様な分野に導入が進んでいます。
しかし、日本における生成AIの活用は、国際的な潮流と比較して大きな差があることが、総務省が発表した「令和7年版情報通信白書(概要)」から明らかになっています。これは単なる技術の遅れなのでしょうか?それとも、日本の未来を左右する重要な分岐点なのでしょうか?
生成AIとは何か?その驚くべき能力
そもそも生成AIとは、どのような技術なのでしょうか?
生成AIは、人間が与える指示(入力情報)に基づいて、まるで人間が作ったかのような新しいコンテンツを自動的に生成する人工知能のことです。具体的な例としては、皆さんもよくご存知の質問に答えるチャットツールや、テキストから絵や写真を生成する画像生成アプリなどが挙げられます。
これらの技術は、膨大なデータを学習することで、人間には想像もつかないようなアイデアを生み出したり、従来は多くの時間と労力を要した作業を劇的に効率化したりする可能性を秘めています。大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる技術の進展が、この爆発的な進化を牽引しており、巨大な投資が可能な海外のビッグテック企業やスタートアップ企業が開発をリードしています。例えば、OpenAIが発表した「OpenAI o1」のような推論に強いモデルや、中国の新興企業DeepSeekによる「DeepSeek-R1」などがその例です。
世界と日本の利用状況、その大きな差
「令和7年版情報通信白書」によると、日本の個人の生成AIサービス利用経験率は、2024年度調査で約27%にとどまっています。これは2023年度調査と比較して約3倍に大きく上昇したものの、主要国と比較すると依然として低い水準です。
具体的に他国の利用率を見てみましょう:
- 中国:81.2%
- 米国:68.8%
- ドイツ:59.2%
- 日本:26.7%
このデータは、日本が世界のAI活用から大きく遅れを取っている現状を浮き彫りにしています。
さらに、利用率には世代間のギャップも顕著です。日本の20代では約45%が利用経験があるものの、60代では15.5%と大幅に低くなっています。
企業における生成AIの活用方針についても同様の傾向が見られます。生成AIを活用する方針を定めている企業の割合は、日本全体で約50%であり、2023年度の約43%からは増加したものの、こちらも他国と比較すると低い水準です。特に、大企業では約56%が方針を定めているのに対し、中小企業では約34%にとどまっています。
なぜ日本では生成AIの利用が進まないのでしょうか?白書や関連情報によると、主な理由として「生活や仕事に必要ない」「使い方がわからない」といった声が多く挙げられています。これは、技術の普及度だけでなく、教育や情報へのアクセス、さらには日本独自の文化的背景や慎重な姿勢も関係している可能性が指摘されています。
なぜ今、生成AIとの向き合い方が問われるのか
生成AIは単なる流行りではなく、社会の仕組みや働き方を根本から変える力を持っているとされています。もし日本がこの流れに乗り遅れ、国際的な活用との差が広がり続ければ、将来的に国の生産性や国際競争力に影響が出る可能性があります。
情報通信白書は、デジタル技術が社会経済活動に浸透し、「社会基盤」としての存在感を増す中で、その負の影響も一層大きくなる恐れがあると指摘しています。AIを含むデジタル技術のリスクも増大する中で、日本がこの技術にどう向き合うかは非常に重要です。
一方で、「条件が整えば使いたい」と考える人も多く、潜在的なニーズは高いこともわかっています。利用率が低いことが必ずしも劣っていることを意味するわけではありませんが、日本が今、重要な岐路に立たされていることは確かだと言えるでしょう。
日本が進むべき道とは何か
このような状況の中で、総務省の白書や関連情報では、日本が今後取り組むべき方向性が示されています。
- 教育の充実: AIリテラシーを高めるための学校教育や社会人向け研修の強化が必要です。インターネットがニュース収集の重要な手段となっている現代において、偽・誤情報の流通・拡散といったデジタル空間の情報流通に関する問題も拡大しており、利用者のICTリテラシー向上は喫緊の課題です。
- 環境整備: 誰でも使いやすいツールやインターフェースの開発が求められています。これは、特に高齢者層を含む幅広い世代へのスマートフォンやSNSの浸透、企業のクラウドサービス利用率の倍増といった「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大をさらに進める上で不可欠です。
- 政策支援: 企業や自治体への導入支援、補助制度の拡充が重要です。中小企業における生成AI活用方針の策定率が低い現状を打破するためにも、政府による後押しが期待されます。
- 情報発信: AIの利点や安全性についての啓発活動を強化し、国民の不安を払拭し、理解を深める必要があります。
また、白書では、通信基盤やデータセンターの外国依存についても懸念が示されており、技術だけでなく経済安全保障の面でも「自律性」が問われています。海外プラットフォーム事業者が日本国内で大きな存在感を発揮し、デジタル関連サービス・財の貿易赤字額が拡大傾向にある中で、強靭なデジタル基盤の確保と、デジタル分野での競争力向上を通じた日本の自律性確保が重要だと強調されています。
幸いなことに、日本でもAIの研究開発は進んでいます。世界のAI活力ランキングでは米国や中国に劣るものの、日本発の大規模言語モデル(LLM)の開発も盛んです。産業技術総合研究所と東京科学大学による「Swallow」や、富士通とCohereによる「Takane」、サイバーエージェントの「CyberAgent LM3-22B-Chat」、Preferred Networksグループの「PLaMo-100B」といった独自開発や日本語能力を強化したモデルが登場しており、高性能な小型モデルの開発も活発化しています。
これらの取り組みは、激甚化する災害への対応、少子高齢化に伴う労働力不足や地方経済の低迷といった社会課題の解決、そして経済活性化・経済成長といった日本の主要な課題に対して、デジタル技術が貢献する可能性を示しています。
まとめ:日本は岐路に立つ
生成AIの活用は、これからの日本社会のあり方を大きく左右する可能性を秘めています。日本の利用率はまだ低いものの、その慎重な姿勢や潜在的なニーズ、そして活発化する国内のAI開発を踏まえると、単純に「遅れている」と断言することはできません。
しかし、国際的なデジタル活用の大きな潮流の中で、日本が重要な岐路に立たされていることは確かです。私たち一人ひとりがこの「分岐点」に立っていることを意識し、生成AIという強力なツールとどう向き合い、どう使いこなしていくのかを真剣に考える時が来ていると言えるでしょう。
引用元:
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 令和7年版情報通信白書(概要)
- 生成AIとどう向き合う?個人利用26%で問われる日本の未来の分岐点 | DXPOカレッジ
- 生成AIとどう向き合う?個人利用26%で問われる日本の未来の分岐点 | DXPOカレッジ
- 生成AIとどう向き合う?個人利用26%で問われる日本の未来の分岐点 | DXPOカレッジ
- 生成AI活用、26.7%止まり [速報] 総務省、AI普及と自律を重視 | 四国ニュース | ニュース