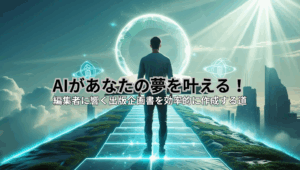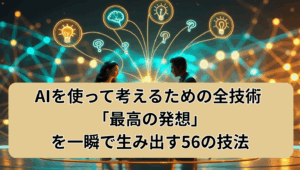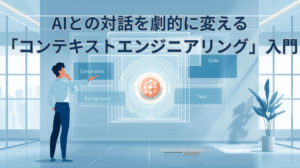「いつか自分の本を出したい!」そんな夢をお持ちではありませんか?その夢を実現するための第一歩が「出版企画書」です。しかし、企画書の作成は時間も労力もかかり、何から手をつけていいか分からないと感じる方も多いでしょう。
ご安心ください。今やAI(人工知能)を最強の相棒にすることで、この出版企画書作りが劇的に効率化し、あなたの夢への道が大きく拓かれます。
この記事では、AIを最大限に活用し、編集者が「この本は売れる!」と唸るような企画書を作成するための具体的なステップを、事例を交えながらご紹介します。
1. 出版企画書とは?あなたの本の「設計図」です
出版企画書とは、あなたの本のアイデアを出版社に伝えるための設計図のようなものです。決まったフォーマットはありませんが、出版社の方、特に編集者が企画書を読んで「こんな本が完成するんだ」「これは売れそうだ」と具体的にイメージできる内容にすることが重要です。
魅力的な企画書には、一般的に以下の要素が含まれます。
- タイトル・サブタイトル、キャッチコピー
- 本書の内容、企画意図・企画背景
- 著者プロフィール
- 読者ターゲット
- 類書と、その本との差別化
- 販促イメージ
- 目次(章構成)
- 見本原稿(数ページ程度)
2. 採用される企画書の3つのポイント
編集者が企画書を評価する際に特に重視するのは、「この本が売れるか?」という市場性です。以下の3つのポイントが共通して重要とされています。
- 明確な企画テーマ: 今までにない新しいテーマや、読者のニーズに合致したテーマを選ぶことが重要です。トレンドや社会課題との関連性を示すと良いでしょう。
- 著者の専門性と影響力: 「なぜあなたがこのテーマについて書くのに適任なのか」という点が問われます。著者自身の専門性や、SNSのフォロワー数、特定の分野での実績などが重視されます。
- 市場性: そのテーマがどのくらい売れるのか、市場の需要があるのかが重要な判断基準です。特に商業出版では、販売冊数が多く見込めるかが重視されます。
3. AIを使った出版企画書の作成ステップ
AIを活用することで、これらの要素を効率的に、かつ魅力的に作成することができます。以下の4つのステップで進めましょう。
ステップ1:自己分析で「強み」を発見する
まずは、ご自身の強みを明確にすることから始めます。AIに自身の情報を入力することで、自分では気づかなかった客観的な強みや独自性を発見できます。
【AIに入力する情報例】
- プロフィール文
- 会社のホームページの内容
- 講演の動画や書き起こし
- 過去のプレゼン資料
- SNS(Facebook, X, ブログなど)の投稿内容
- メディア掲載記事
【AIへの効果的な指示方法(プロンプト例)】
- 「私の強みを5つ箇条書きで抽出してください」
- 「このプロフィールから、どのような本が書けそうか教えてください」
- さらに「どのようなターゲットに対して、どういうテーマで書きそうか」など、掘り下げて質問すると、より精度の高い回答が得られます。
ステップ2:本の目的を設定する
「何のために本を出すのか」を明確にすることも大切です。目的によって、本の内容や構成、マーケティング戦略が変わるためです。
【本の目的の例】
- ブランディング: 専門家としての認知度向上、地位確立
- マーケティング: 新規顧客獲得や事業機会の創出
- メッセージの発信: 世の中に伝えたい理念や価値観の広範な伝達
- 社会貢献: 専門知識や経験の社会還元
これらの目的をAIに伝えることで、目的に合ったタイトルや目次を生成しやすくなります。
ステップ3:ターゲット読者を具体的に設定する
「誰に届けたい本なのか」を具体的に設定しましょう。例えば、「30代から40代の中小企業男性経営者」のように、年齢・性別・職業、抱えている課題や悩み、知識レベルや関心事などを具体的に描くことで、より読者に響く内容にできます。
ステップ4:AIを活用したタイトルと目次の作成
自己分析、目的設定、ターゲット読者の設定ができたら、いよいよAIを使ってタイトル案と目次を作成します。
タイトル案の生成
AIに「〇〇なターゲット向けに、〇〇に関する本のタイトルを10個あげてください」といった形で指示を出すと、複数のタイトル案が生成されます。キャッチーで覚えやすく、内容が想像できるタイトルにするよう指示すると良いでしょう。
【プロンプト例】 「以下の条件を満たす本のタイトルを10個考えてください:テーマは『AI活用による業務効率化』、ターゲットは『中小企業の経営者』、目的は『実践的なAI導入方法の提供』です。キャッチーで覚えやすく、内容が想像できるタイトルにしてください。」
類書調査
生成されたタイトル案の中から気に入ったものを選び、Amazonなどで類似の本(類書)を調べてみましょう。
- 競合の確認: 類似のテーマやタイトルの本が多く出版されている場合は、レッドオーシャン(競合が多い市場)である可能性があります。その場合は、タイトルを差別化したり、独自の切り口を見つけたりする必要があります。
- レビューの確認: 類書のレビューを確認することで、読者のニーズや不満を把握できます。
- 著者のリサーチ: 類書の著者のプロフィールを調べることで、自身の強みとの比較検討ができます。
この調査結果を基に、類書にはない新しい視点や事例の豊富さを盛り込むことで、あなたの本の優位性を示せます.
目次の作成
タイトルが決まったら、AIに「このタイトルで、〇章立ての目次を作成してください。読者を飽きさせない魅力ある目次にしてください。」などと指示を出します。
【プロンプト例】 「『(先ほど決めた本のタイトル)』という本の目次を、6章立てで作成してください。この本の目的は[出版の目的(例:カメラ講座の集客)]です。」 「各章に項目タイトルを10個ずつ作ってください。」
AIが生成した目次はあくまで叩き台です。論理的な流れ、内容の網羅性、読者の学習曲線に合っているかを確認し、章の順序や内容、重点の置き方などを調整しましょう。
【具体的な指示のコツ】
- 「第3章をより実践的な内容にしてください」
- 「今の回答は40点です。80点以上を目指してください」
- 「もっとインパクトを強くして」「キャッチーにして」
AIの回答を磨き上げるコツ
AIとの対話では、具体的なフィードバックが非常に重要です。AIの回答に満足できない場合は、「40点です。80点以上を目指してください」などと具体的に点数で評価したり、「第3章をより実践的な内容にしてください」と内容を指示することで、より質の高い提案を引き出すことができます。
また、生成された目次をWordなどにコピーペーストし、印刷して確認するアナログでの確認も、デジタル画面では気づかない点を発見できるため有効です。
4. AIと人間の協働:効率と創造性の融合
AIは強力なツールであり、アイデア出し、構成案の作成、本文の下書き作成において驚異的な力を発揮します。例えば、YouTubeチャンネル「40歳からのAI活用塾」の海野氏の事例では、Gemini 2.5 Proを使って週末の1.5日で5.5万字の本を書き上げた経験を紹介しています。AIが本文の下書きを作成し、人間はそれを編集、修正、調整する作業に集中できるため、執筆プロセスを爆速化できます。
しかし、最終的な判断と創造性は人間が担うものです。AIが生成した「叩き台」に、あなたの経験や情熱、独自の視点を加えることで、企画書は魂のこもった唯一無二のものになります。
AIはチャットが長くなると、出力の質が落ちるなどの限界もありますが、その際は新しいチャットに移行し、人間の側で体裁を整えるなどの調整を行うことで対応できます。AIと人間の強みを組み合わせることで、採用される確率の高い出版企画書を効率的に作成できるのです。
5. Kindle出版という具体的な道筋の例
出版企画書の作成は、商業出版だけでなく、Kindle出版のような自己出版においても非常に役立ちます。海野氏は、AIを活用したKindle出版の魅力を以下のように語っています。
- 無料で出版可能: コンサルなどを依頼せずとも、自分一人で完全に無料で出版できます。
- 最大70%の印税: 販売価格に応じて、高い印税率が設定されます。
- 知識や経験の資産化: あなたの持つ専門知識や経験が、本という形で資産になります。
- 自分のペースでできる: 週末や夜の時間を活用し、数時間ずつでも執筆を進められます。
- 在庫リスク、初期費用なし: 紙の本でもAmazonが注文後に印刷・発送するため、在庫を抱えるリスクがありません。
- 不労所得の可能性: 月に数千円から数万円の収益を実現している例もあります。
- ブランディングに有効: 講師業やコンサルティング業など、専門家としての権威性を高めるツールになります。
このように、AIは出版のハードルを劇的に下げました。企画書の作成から、本文の執筆、表紙デザインのヒント、さらにはKindle出版の具体的な手続きに至るまで、AIは強力なアシスタントとなり得ます。
最後に
AIは、あなたの本のアイデアを形にするための強力な味方です。このブログ記事で学んだAI活用術を参考に、ぜひあなたの素晴らしい知識やメッセージを、一冊の本として世の中に届けてみてください。ご自身の強みと読者のニーズを深く掘り下げ、AIを賢く活用することで、魅力的な出版企画書が完成するはずです。
小さな一歩から、あなたの週末作家、あるいは商業作家への道が拓くかもしれません。