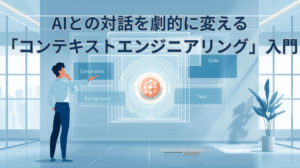「何か新しいアイデアない?」
会議でそう振られて、頭が真っ白になった経験はありませんか?
- 企画書を出すたびに、いつも似たような内容になってしまう…
- 限られた時間で、質の高いアイデアを大量に求められてツラい…
- そもそも「良いアイデアの出し方」が、根本的にわかっていない…
もし、あなたがこんな悩みを抱えているなら、この記事はきっとあなたのためのものです。
実は、私たちが「うーん、この企画、なんだかパッとしないな…」と感じるとき、その原因は文章の表現やデザインの巧みさ以前に、そもそもの「アイデア」そのものが弱いケースがほとんどです。
逆に、アイデアがダイヤモンドの原石のように光っていれば、多少荒削りな企画書でも「これはイケるぞ!」という強いエネルギーを放ちます。
つまり、仕事の成果を左右するのは、小手先のテクニックではなく、核となる「アイデアの質と量」なのです。
とはいえ、「じゃあ、どうやってその“良いアイデア”を出すの?」という壁が、私たちの前に立ちはだかります。まるで、分厚くて高い、コンクリートの壁のように…。
「アイデアは天才のひらめき」という大きな誤解
かつての私は、こう思っていました。
「アイデアって、結局は一部の天才がひらめく“天からの授かりもの”なんじゃないか?」と。
しかし、ある有名な言葉が、その凝り固まった考えを打ち砕いてくれました。
「アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせである」
あなたも一度は耳にしたことがあるかもしれません。
この言葉を聞いた瞬間、「なんだ、ゼロから生み出す魔法じゃなくて、知っているものの“組み合わせ”でいいのか!」と、心がフッと軽くなったのを覚えています。
例えば、今や世界中の人が使う「スマートフォン」。これも「携帯電話」×「音楽プレイヤー」×「インターネット端末」という、既存の要素の新しい組み合わせですよね。他にも、「回転寿司」は「お寿司屋さん」×「工場のベルトコンベア」という組み合わせから生まれました。
でも、すぐに次の疑問が湧いてきます。
- その「組み合わせるための要素」って、どうやって見つけるの?
- 「新しく組み合わせる」って、具体的にどうやるの?
わかるようで、わからない。できそうで、できない。
アイデア出しとは、なんとももどかしい作業です。
そんな長年のモヤモヤを、一気に吹き飛ばしてくれたのが、今回ご紹介する一冊でした。
▼アイデア出しに悩むすべての人へ
『AIを使って考えるための全技術 「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法』
アイデアは「連想→想像→創造」の3ステップで生まれる
本書の核心は、アイデア発想のプロセスを「連想 → 想像 → 創造」という、誰でも実践可能な3つのステップに分解してくれている点です。
最初に「連想」によって物事や概念が結びつき、広がりを持ちます。次に「想像」では、連想で得たことをヒントにして自由に発想が拡がります。そして最後の「創造」で、これまでに想像したヒントがアイデアとして具体化していきます。
――引用『AIを使って考えるための全技術』p.38
これこそが、先ほどの「既存の要素を新しく組み合わせる」ための、具体的な実践ルートなのです。
そして、この全プロセスを、AIが最強の壁打ち相手として手伝ってくれるのが、本書が示す新しい時代の「考え方」です。
具体例:「新しいエナジードリンク」のアイデアを考えてみる
この3ステップを、AIと一緒に実践するとどうなるか、具体例で見てみましょう。
【ステップ1:連想】AIに思考のタネをまいてもらう
まず、ChatGPTのようなAIに「エナジードリンク」というテーマで、関連するキーワードを大量に出してもらいます。
あなた:
「新しいエナジードリンクのアイデアを出したい。関連するキーワードを連想して、カテゴリー別にリストアップして。」
AIの出力(例):
- ターゲット層: ビジネスパーソン, 学生, アスリート, eスポーツ選手, 主婦
- 成分: カフェイン, アルギニン, ビタミン, 天然素材, フルーツ, ハーブ, 無添加
- コンセプト: 集中力UP, リラックス, 健康志向, 自然派, 高級感, サブカル
- シーン: 仕事中, 勉強前, 運動後, ゲーム中, 朝の一杯
この段階では、自分一人では思いつかなかったような単語(例えば「主婦」「リラックス」「ハーブ」など)がAIから出てくることで、思考の範囲が一気に広がります。
【ステップ2:想像】AIと対話しながらアイデアを膨らませる
次に、連想で得たキーワードを組み合わせて、AIと対話しながら自由に発想を広げます。
あなた:
「面白い組み合わせを探したい。『主婦』と『リラックス』と『ハーブ』を組み合わせたエナジードリンクのコンセプトを5つ考えて。」
AIの出力(例):
- 「午後のティータイム・エナジー」: カモミールやラベンダー配合。家事の合間にホッと一息つきながら、もうひと頑張りできる微炭酸ドリンク。
- 「週末リセット・チャージ」: レモングラスとジンジャーをベースに。心と体をリフレッシュさせ、週明けへの活力をチャージするコンセプト。
- …(続く)
このように、AIに具体的な「お題」を投げかけることで、アイデアのヒントとなるコンセプトが次々と生まれてきます。
【ステップ3:創造】AIにアイデアを具体化してもらう
最後に、出てきたコンセプトを具体的な商品アイデアに落とし込みます。
あなた:
「『午後のティータイム・エナジー』のコンセプトが面白い。この商品のターゲット、ネーミング案、キャッチコピー、商品の特徴を具体的に考えて。」
AIの出力(例):
- ターゲット: 30〜40代の忙しい主婦、子育て世代
- ネーミング案: 「私の、ごほうびブースト」「ゆるっとチャージ」「午後3時の魔法」
- キャッチコピー: 「もう、カフェインに頼らない。ハーブの力で、私の午後をもう一度オンにする。」
- 商品の特徴: カフェインゼロ。国産オーガニックハーブ使用。ボトルがおしゃれで、キッチンに置いても生活感が出ないデザイン。
いかがでしょうか。
たった数回のやり取りで、具体的で説得力のあるアイデアの骨子が完成しました。これが、AIと一緒に「考える」ということの威力です。
ただのプロンプト集じゃない!思考の“OS”をアップデートする一冊
「なるほど、便利なプロンプトが載っている本なんだな」
そう思った方もいるかもしれませんが、本書の価値はそこだけではありません。もちろん、コピペで今すぐ使えるプロンプトは大量に収録されており、特典としてダウンロードまで可能です。
しかし、本書が本当に素晴らしいのは、そのプロンプトの裏側にある「なぜ、そう考えるのか?」という思考の構造や意図が、著者の思考回路とともに、これでもかというほど丁寧に解説されている点です。
- なぜ、この質問をAIに投げかけるのか?
- AIの膨大な出力から、どこに着目し、どう選び取るのか?
- どうすれば、AIの能力を最大限に引き出し、思考を深められるのか?
ページ数は682ページと辞書のような分厚さですが、対話形式でサクサク読めて、まるで著者の思考を追体験しているかのような感覚に陥ります。
本書は、単なるAIの使い方マニュアルではなく、AIという最高の相棒と共に、自分自身の「考える力」そのものを鍛え上げるための“思考の筋トレ本”なのです。
AIは「効率化」の道具から「思考を拡張する」パートナーへ
アイデアが出ないとき、私たちは「自分の引き出しが少ないな…」「思考が浅いな…」と、一人で落ち込んでしまいがちです。
しかし、そこにAIというパートナーがいればどうでしょう?
行き詰まったときには別の角度から問いを投げかけてくれ、自分では思いもよらない斬新な切り口を提示してくれる。AIとの対話は、まるで優秀な壁打ち相手とブレストをしているかのようです。
その結果、「あれ!?今までとは全く違う視点で物事を考えられている!」と、自分の思考が拡張されていくのを実感できるはずです。
この感覚こそが、これからの時代を生き抜くための、本質的なスキルになっていくと私は確信しています。
- もう、プロンプトのコピペで終わるのはやめたい
- AIを使って、本物の思考スキルを身につけたい
- 自信を持って「これだ!」と言えるアイデアを生み出せるようになりたい
もしあなたがそう願うなら、この本は間違いなくあなたの力になってくれます。
考えることをAIに丸投げして思考停止に陥るのではなく、AIと共に考え、自分の能力を最大限に引き出す。
そんな新しい働き方を、この本から始めてみませんか?
ビジネスの現場で、アイデアの質とスピードの両方が求められるすべての人に、自信を持っておすすめします。
▼AI時代を勝ち抜く「考える力」を手に入れる
『AIを使って考えるための全技術 「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法』