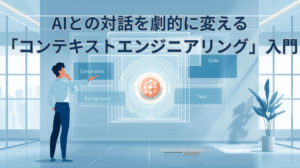「AIに仕事を任せれば楽になる」
「AIに企画書を考えてもらおう」
そんな風に考えていませんか?もちろん、それもAIの便利な使い方の一つです。しかし、AIの真価はそれだけではありません。
今回ご紹介するのは、書籍『AIを使って考えるための全技術』の著者、石井力重氏による解説です。AIを単なる「考えさせる」道具ではなく、「一緒に考える」パートナーとして活用することで、人間の創造性を飛躍的に高める新時代の思考スキルが紹介されています。
「AIに考えてもらう」から「AIを使って考える」へ
石井氏が提唱する最も重要なコンセプトは、「AIに考えてもらうのではなく、AIを使って考える」という姿勢です。これは「人機共想(じんききょうそう)」と呼ばれ、人と機械(AI)が共に思考する新しい働き方を指します。
大事なことは「AIに考えてもらう」んじゃなくて、「AIを使って考える」
この「人機共想」を実践することで、私たちはAIの能力を最大限に引き出し、これまでになかった質の高いアウトプットを生み出すことができるのです。
なぜ「AIを使って考える」べきなのか?3つのメリット
AIを思考のパートナーにすることで、以下の3つの大きなメリットが得られます。
- 量:大量のアイデアを簡単に獲得できる
人間だけでは思いつかないような、多種多様なアイデアを瞬時に得ることができます。 - 効率:時間的な効率化ができる
リサーチやブレインストーミングにかかる時間を大幅に短縮し、より本質的な思考に集中できます。 - 質:アイデアを昇華させられる
AIが出したアイデアをヒントに、人間がさらに思考を深めることで、アイデアの質を格段に向上させることができます。
石井氏は、「AIは『量・効率・質』の3つの面で、思考を支えてくれる」と述べ、このスキルがやがてビジネスパーソン必須のスキルになると断言しています。
どのAIを選ぶべき?主要AIの特徴を比較
動画では、代表的な5つの生成AIが紹介され、それぞれの特徴が分かりやすく解説されています。
| AI名 | 開発企業 | 特徴(著者の私見) |
| ChatGPT | OpenAI | 汎用性が高く、創造的な指示も得意。ハルシネーションの可能性を抑え込まず、創造的対話を解放している側面がある。 |
| Claude | Anthropic | 長い文章の処理が得意。無料でも高性能で、ChatGPT以外のアイデアを得たい場合に便利。 |
| Copilot | Microsoft | 「創造的な回答を」と明確に指示すると、創造的なタスクにも対応。ビジネス文章で使いやすい回答が得意。 |
| Gemini | 最新情報にアクセス可能。他のAIとは方向性が結構違うものを出してくるため、ブレストに便利。 | |
| Perplexity | Perplexity | 検索に優れ、質問に対して正確な回答を提供。探索的要素の多い創造タスクに便利。 |
この表は、上に行くほど「生成能力(創造性)が高いAI」、下に行くほど「良く調べて回答するAI」という傾向でまとめられています。目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。
実践!AIと一緒に「ネコ用商品」のアイデアを考えてみた
実際にAIと対話しながら「ネコ用商品」のアイデアを生み出すプロセスを紹介。。。
ステップ1:困りごとを洗い出す
まず、「ネコを飼っている人や、飼い猫自体が困っていること」をAIにリストアップさせます。「抜け毛が多い」「留守番時の孤独」など、具体的な困りごとが多数挙げられました。
ステップ2:既存品のストレスを探る
次に、「既存のネコ用商品に対するストレス要因」を質問します。「すぐに壊れる」「デザインがインテリアに合わない」といった、ユーザーの不満点が明らかになりました。
ステップ3:新たな視点を取り入れる(新しい地平の探索)
ここからが「人機共想」の真骨頂です。AIが出したアイデアと、人間がそれを見て思いついたアイデア(例:専門家による猫の毛洗浄サービス)を全てAIに見せ、「これらのアイデア群の偏りから、まだ考えられていない方向性(=発想の抜け・未開拓ゾーン)を探して」と指示します。
その結果、AIは以下のような、これまでの議論では出てこなかった新しい視点を提示しました。
- 猫“自身”の自立・満足(猫が自分で考え、選び、行動できる商品)
- 多頭飼い・相性調整(複数猫間の関係性ケア)
- 猫の老化・介護領域
- 外猫・半外猫への対応
このように、AIとの対話を繰り返すことで、人間だけでは気づきにくい「思考の盲点」を発見し、アイデアの幅と奥行きを一気に広げることができたのです。
まとめ:AIを思考の壁打ち相手にしよう
この動画は、AIが決して人間の思考を代替するものではなく、むしろ私たちの創造性を刺激し、思考を加速させるための最高のパートナーであることを教えてくれます。
ポイントは以下の通りです。
- AIに「考えてもらう」のではなく「AIを使って考える」。
- AIとの対話を通じて、自分の思考の盲点や偏りに気づく。
- AIが出した多様なアイデアをヒントに、人間がさらに発想を広げる。
AIとの対話は、まるで優秀な壁打ち相手とブレインストーミングをするようなもの。あなたも「人機共想」を実践し、AI時代に必須の思考スキルを身につけてみてはいかがでしょうか。
【後編】AIとの対話でアイデアが爆発!『AIを使って考えるための全技術』実践ケーススタディ
前回の記事では、書籍『AIを使って考えるための全技術』の著者、石井力重氏が提唱する新時代の思考スキル「人機共想」の概要をご紹介しました。AIを単なる道具ではなく、「共に考えるパートナー」として活用することで、人間の創造性を最大限に引き出すという考え方です。
今回の後編では、動画で実演された「AIと共にアイデアを考える」ケーススタディを詳しく解説します。「ネコ用商品」というテーマで、ゼロから魅力的なアイデアが生まれるまでの具体的なプロセスを見ていきましょう。
Step 1:困りごとを洗い出す「起点」づくり(技法47・48)
アイデア出しの第一歩は、課題の発見です。石井氏はまず、AIに2つの質問を投げかけます。
- 主な困りごと(技法47): 「ネコを飼っている人や、飼い猫自体が困っていること」をリストアップさせる。
- 既存品のストレス(技法48): 「既存のネコ用商品に対する不満やストレス要因」を挙げさせる。
AIは、「抜け毛が多い」「留守番時の孤独」「すぐに壊れる」「デザインがインテリアに合わない」といった、飼い主と猫双方の視点から具体的な困りごとや不満を瞬時にリストアップしました。
面白いのは、このAIとの対話を通じて、人間の頭の中にも様々なアイデアの「起点」が湧き出てくることです。
AIが提示したキーワードを見るだけで、「そういえば、うちの猫も…」「こんな商品があったらいいのに」と、自然と人間の思考も活性化していくのです。
Step 2:強制的に発想を飛ばす「多様な特徴」(技法1)
次に、石井氏は非常にユニークな指示を出します。それは、「特徴が異なる動物や生物を10個あげて、その特徴を活かしたネコ用商品のアイデアを7つ考えてください」というものです。
これは、あえて無関係な要素を掛け合わせることで、凝り固まった思考の枠を壊し、斬新なアイデアを生み出すためのテクニックです。
AIは、カメレオン、フクロウ、カタツムリなどの特徴から、以下のようなユニークなアイデアを提案しました。
- カメレオン → カモフラージュベッド: 部屋に馴染む、色柄が変わる猫ベッド
- フクロウ → 夜間静音おもちゃ: 夜でも静かで、猫にだけ見えるおもちゃ
- カタツムリ → 自走式粘液クリーナー: 小型ロボットがコートの表面を這い、粘着ローラーで猫毛を回収
ここで重要なのは、人間の役割です。石井氏はAIの回答を見て、「おもちゃのアイデアに偏っているな」という気づきを得ます。そして、「飼い主の衣類ケアという視点も面白いのでは?」と、対話の方向性を修正していくのです。
Step 3:思考の盲点を発見する「新しい地平の探索」(技法18)
ここからが「人機共想」のクライマックスです。石井氏は、これまでのAIとの対話で出た全アイデア(29案)と、その中で人間が考えたこと(「衣類ケアも面白そう」など)を全てAIにインプットします。
その上で、こう指示を出しました。
「これまでのアイデア群の偏りを整理し、まだ考えられていない方向性(=発想の抜け・未開拓ゾーン)を探してください」
これは、人間だけでは気づきにくい「思考の盲点(認知バイアス)」をAIに発見させるという、非常に高度なテクニックです。
この指示を受け、AIはこれまでとは全く異なる、新たなアイデアの方向性を4つ提示しました。
- 猫“自身”の自立・満足: 猫が自分で考え、選び、行動できる商品
- 多頭飼い・相性調整: 複数猫間の関係性ケアやストレス対策商品
- 猫の老化・介護領域: シニア猫向けの生活サポート、見守り
- 外猫・半外猫への対応: 屋外・屋内の行き来が多い猫のためのグッズ
これらの視点は、最初の「困りごと」のリストアップだけでは決して出てこなかった、まさに「未開拓ゾーン」です。AIとの対話を重ね、人間が舵取りをすることで、アイデアの地平そのものを大きく広げることに成功したのです。
まとめ:AIは最強の「思考パートナー」だ
今回のケーススタディは、AIが単に答えを出す機械ではなく、人間の思考を刺激し、新たな視点を提示してくれる強力なパートナーであることを示しています。
- AIに問いを投げかけることで、思考の「起点」を得る。
- AIの回答から偏りや気づきを得て、人間が対話の「舵を取る」。
- 対話の履歴をAIにフィードバックし、「思考の盲点」を壊してもらう。
このサイクルを繰り返すことで、一人では決して辿り着けない、創造的で魅力的なアイデアを生み出すことができます。
あなたも書籍『AIを使って考えるための全技術』を手に取り、AIとの対話を通じて、思考の限界を超える体験をしてみてはいかがでしょうか。
承知いたしました。
動画『AIを使って考えるための全技術』の中から、AIを使いこなし、アイデアを生み出すための具体的な**「Tips(ヒントやコツ)」**を抽出し、分かりやすく整理しました。
AI使いの達人になる!『AIを使って考えるための全技術』から学ぶ、今日から使える実践Tips集
AIを使いこなすには、単に質問を投げるだけでは不十分です。AIとの対話の質を高め、その能力を最大限に引き出すためには、いくつかのコツが存在します。
ここでは、動画で紹介された「AIとの対話術」や「思考を加速させるためのヒント」を、明日からすぐに使えるTipsとしてまとめました。
【マインドセット編】 AIとの向き合い方を変える3つの心得
テクニックの前に、まずAIに対する考え方をアップデートすることが重要です。
- 「考えてもらう」から「共に考える」パートナーへ
最も重要な心構えです。AIを「答えを出す機械」と捉えるのではなく、アイデアを出し合う**「思考の壁打ち相手」として捉えましょう。この「人機共想」**の姿勢が、創造的なアウトプットを生む第一歩です。 - 「使える/使えない」で即断しない。情報のシャワーを浴びる
AIが出してきた大量のアイデアを、すぐに「使える」「使えない」と判断するのは創造性の観点からは望ましくありません。一見無関係に見える情報や、とんちんかんな回答も、ごった煮の**「情報のシャワー」**として浴びることで、思わぬアイデアのヒントになることがあります。 - 変な回答も「面白い!」と受け入れてみる
AIが出す突拍子もないアイデアや、少しずれた回答を否定せず、「面白い!」と受け入れてみましょう。そこから**「悪ノリして膨らませてみる」**ことで、自分だけでは思いつかなかった創造的なアイデアに繋がることがよくあります。
【実践テクニック編】 AIの能力を120%引き出す対話術
具体的な対話の場面で役立つTipsです。
基本の5つの注意点
- はっきりと具体的に聞く: 曖昧な質問(例:「いろんな方法」)ではなく、「5〜7個の個別の方法」「高価格帯で」など、具体的に指示しましょう。
- 全体像を伝えつつ、聞く: 短い質問はAIが戸惑います。「社会人1年目向けに調べ物を節約できるアプリ企画」のように、背景や目的を伝えることで回答の精度が上がります。
- いっぺんに聞かずに、1つずつ聞く: 複数の質問をまとめると回答が不明瞭になりがちです。基本は「1問1答」を心がけましょう。
- ハルシネーション(もっともらしい嘘)に注意: AIは虚偽の情報をあたかも正しいかのように答えることがあります。重要な情報(数値、固有名詞など)は必ず裏取りを行いましょう。
- 自社の「守秘義務ルール」を遵守: 機密情報の入力は絶対に避けましょう。公開情報だけで質問するのが安全です。
アイデアを広げ、深めるための応用コマンド
- 褒めて伸ばす:「いいですね」で方向性を教える
AIが出した回答に対して「いいですね」と返すと、AIは「今出したアイデアは気に入ってもらえた」「このテイストや粒度は合っているんだな」と認識し、その後の回答の方向性を維持・改善してくれます。 - 思考を整理させる:「ここまでの内容をリスト化して」
対話が長くなり情報が散らかってきたら、一度アイデアをリスト化するよう指示しましょう。これにより、AIと人間の認識を揃え、次のステップに進みやすくなります。 - あえて縛らない:「アバウトな質問」で発想を飛ばす
ブレインストーミングの初期段階では、あえて商品タイプなどを指定せず、「ネコ用商品について」のようにアバウトな質問を投げることで、AIに思考の制約を外させ、予想外のアイデアを引き出すことができます。 - 思考を深掘りする:「どうすれば実現できる?」と素直に聞く
AIが出したアイデア(例:「自走式クリーナー」)に対して、「どうやって実現するんだろう?」と気になったら、その疑問をそのままAIにぶつけてみましょう。AIは具体的な実現方法の案を出してくれ、アイデアを企画へと昇華させる手助けになります。
【情報整理編】 思考のログを残す習慣
- 良いアイデアは別ファイルに「コピペ」する
AIとの対話は情報爆発が起きやすく、良いアイデアもすぐに埋もれてしまいます。気になったヒントやアイデアは、その都度別のファイルにコピー&ペーストして保存する習慣をつけましょう。 - 対話中に浮かんだ自分の考えも「メモ」する
重要なのはAIの出力だけではありません。対話の途中で自分の頭に浮かんだ考えや疑問も、すぐにメモしておきましょう。後から見返したときに、思考のプロセスを辿る貴重な手がかりとなります。
これらのTipsを意識するだけで、AIとの対話の質は劇的に向上します。AIを最強の「思考パートナー」として育て上げ、あなたの中に眠る創造力を解き放ちましょう。