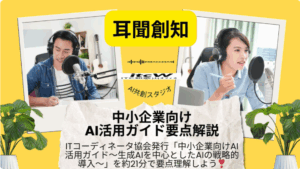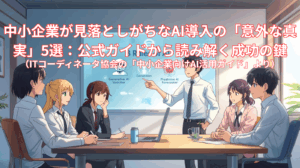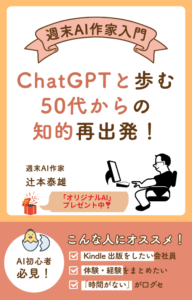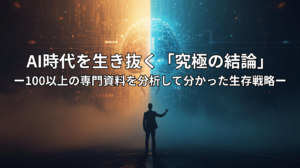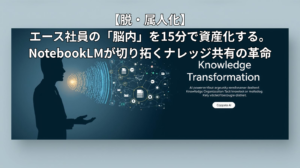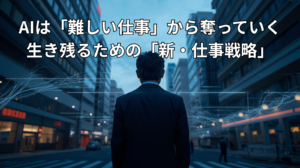「AIって最近よく聞くけど、うちみたいな中小企業には関係ないかな…」
「何から手をつければいいのか、さっぱりわからない…」
そんなお悩みをお持ちの中小企業の経営者やご担当者の皆様、必見です!
今回は、ITコーディネータ協会が発行した「中小企業向けAI活用ガイド~生成AIを中心としたAIの戦略的導入~」の要点を、対談形式の解説動画を基にわかりやすくブログ記事にまとめました。
この記事を読めば、あなたの会社がAIを味方につけ、ビジネスを次のステージへ進めるための具体的なヒントが見つかるはずです。
動画で学ぶ「中小企業向けAI活用ガイド」
まずはこちらの動画をご覧ください。記事と合わせて見ていただくと、より理解が深まります。
動画の要点解説(文字起こし)
女性: こんにちは、The Deep Diveの時間です。今回はですね、あなたのような中小企業の経営者や、あるいは担当者の方が、今すごく話題のAI、特に、えっと、生成AIとどう向き合って、自社の力にしていくか、その核心の部分を深掘りしていきたいと思います。
で、今回頼りになるのがこちら。ITコーディネータ協会、生成AI研究会がまとめた「中小企業向けAI活用ガイド」です。このガイドを、まあ羅針盤みたいにして、AI導入っていう航海で本当に大事なポイントとか、実践的なヒントをあなたと一緒に見つけ出す。これが今回のミッションですね。
ガイドの冒頭にもありましたけど、人手不足とか、予測できない市場の変化とか、こういうまあ荒波の中で、AIってもう「あれば便利」っていうレベルじゃなくて、なくてはならない羅針盤、つまり必須の経営課題なんだということなんですよね。
男性: ええ、まさにその通りだと思います。ただ、「必須」って言われても、うーん、じゃあどこから手をつけていいのかとか、何か大きな投資が必要なんじゃないかって、あの不安に感じる方もたぶん多いでしょうね。
で、このガイドの非常に優れている点というのは、単なる技術の解説にとどまらず、経営の視点から「じゃあ具体的にどう動けばいいのか」という、その行動計画に落とし込めるような非常に実践的な知恵が詰まっている、そこなんですよ。本当に中小企業の現実を踏まえた、地に足のついたガイドと言えるんじゃないでしょうか。
女性: なるほど。実践的な知恵、ですか?それは心強いですね。では早速、その知恵の源泉であるガイドを一緒に読み解いていきましょうか。
まず、あの、基本の確認から。そもそもAIって何なんだっていう点ですけど、ガイドでは「人間が行う知的活動(まあ判断したり学んだり何かを創り出したり)、そういうことをコンピューターで再現したり、拡張しようとしたりする技術の総称」と、こうありますね。
で、今特に注目されているのが、「生成AI」「認識AI」「予測AI」のこの3つだと。世間では生成AIがこう花形っていう感じですけど、この3つの使い分けっていうのが結構重要になってきそうですね。
男性: おっしゃる通りですね。ええ。生成AIっていうのは、まあ文章とか画像とか、そういうゼロから何かを生み出すのが得意なAIですよね。
一方で、その認識AI、これは画像とか音声、文字といった、今すでにある情報を理解する技術なんです。例えば、目で見て確認するような作業とか、耳で聞いて文字起こしするみたいな作業を代わりにやってくれる。
そして、3つ目の予測AIは、過去のデータをもとにして未来を読み解く技術。需要予測なんかはその典型例ですね。
多くの方がまず生成AIに目が行きがちだと思うんですが、実はですね、日々の業務の効率化っていう点で考えると、認識AIによる自動化とか、あるいは予測AIによる「先読み」の方が、最初に大きな効果を実感できる「隠れた主役」かもしれないんですよ。
女性: へえ、「隠れた主役」ですか。それは面白い視点ですね。生成AIだけじゃなくて、認識AIとか予測AIにもちゃんと目を向けるべきだと。じゃあ、これらのAIが中小企業にとって重要だというのは、具体的にどういうメリットがあるからなんでしょうか?やっぱり人手不足の解消とかそういうことになってくるんですかね?
男性: はい。まず、人手不足への対応としての業務効率化、これは大きな柱の一つですね。認識AIによる単純作業の自動化なんかがまあ典型です。
それに加えて、市場の変化に素早く対応するためのデータに基づいた意思決定。これは予測AIの得意分野ですね。
さらに、生成AIなんかを活用した新しい価値の創造、つまりイノベーション。これも期待できます。ガイドも指摘しているように、これらはまさに中小企業が抱えている課題の解決に直結してくるわけです。
実際、あの、東京商工会議所が2024年に行った調査では、もうすでに45%以上の中小企業が生成AIを活用している、あるいは検討しているというデータもあるんです。これはもう、「ちょっと様子見で」っていう段階ではなくて、使わないこと自体がリスクになる、そういう状況を示していると言えるんじゃないでしょうか。
女性: 45%以上…へえ。思ったよりもかなり進んでるんですね。ちなみにAIってなんか最近急に出てきたようなイメージがありますけど、ガイドを見ると結構歴史があるんですね。4つの世代があると。
男性: ええ、そうなんです。まあ、簡単に触れておくと、最初はルールに基づいて推論する、まあ「推論・探索の時代」。次に専門家の知識をシステムに入れた「エキスパートシステム」。そして、データからAI自身が自律的に学ぶ「深層学習(ディープラーニング)」。これが第3世代。
で、現在が、コンテンツを創り出す第4世代の「生成AI」と、こういう流れになっています。ここで重要なのは、この第4世代の生成AIが、それ以前の認識AIとか予測AIとうまく連携できるようになったという点なんです。
例えばですね、現場の何か異常な状態をカメラ、つまり認識AIで捉えて、そのデータを分析して、いつ故障しそうかというのを予測AIが割り出す。そして、その対応策を生成AIが文章で提案するといった、そういう連携が可能になってきたわけです。これによって、データ収集して、分析して、アクションを提案するという一連の流れを、かなりの部分自動化できる可能性が出てきたわけです。これが今のAI活用の非常に大きなポイントだと思いますね。
女性: なるほど。3つのAIが連携することで、単なる作業の代行以上のことができる可能性があるということですね。では、より具体的に、あなたがAIをどう使えるのか、ガイドに載っている活用シナリオをちょっと見ていきましょうか。まずはやっぱり話題の生成AIからですね。
男性: ええ。生成AIの、まあ得意技としては、文章とかアイデアの壁打ち相手、っていうのが分かりやすいでしょうかね。企画書とか提案書、あとはメールマガジン、会議の議事録、こういう文章のまず「たたき台」を作るのはもうお手の物です。
ほかにも、広告バナーみたいな画像のデインを試作したりとか、新しい商品とかサービスのアイデア出しを手伝ってもらったり、あとは簡単なプログラムコードの作成なんかも支援してくれますね。
ただし、あの、非常に重要な注意点として、ガイドが強調しているのは、あくまでもアシスタントとして使うということなんです。完璧なものはまあ期待しない。初稿とか発想のヒントをもらうという位置づけで、最後の仕上げは必ず人間がチェックして手を入れる。このスタンスが非常に肝心です。
女性: なるほど、「完璧を求めすぎない」と、わかりました。次に、認識AIはどうでしょう?こちらはさっき「隠れた主役候補」という話でしたよね?
男性: はい、そうですね。こちらは本当に日々の業務改善にかなり直結しやすい技術だと思います。例えば、紙の請求書とか注文書をスキャンして文字を読み取ってデータ化する、あの「OCR(光学文字認識)」ですね。これは言わば、AIが目で文字を読んでくれるようなものです。
ほかにも、工場のラインで製品の傷とか汚れを目で見てチェックする代わりにAIが行う「外観検査」。これは「画像認識」ですね。あとは、会議とかインタビューの音声を自動でテキストにする「文字起こし」。これは「音声認識」。あるいは、多言語での問い合わせにチャットボットが自動で答える、といった活用もあります。
これらは要するに、目で見る、耳で聞く、文字に起こすといった、これまでどうしても人手に頼っていた作業を肩代わりしてくれるので、人的なミスの削減と作業時間の大幅な短縮に大きく貢献することが期待できますね。
女性: いやー、請求書の山に埋もれる月末作業が楽になるかもって想像するだけでちょっと助かりますね(笑)。では、3つ目の「予測AI」。これはどう活用できるんでしょうか?未来を読むというのはすごく魅力的ですけど。
男性: ええ。予測AIは、言わば未来への羅針盤のようなものですね。過去の販売実績データなんかから、将来どれくらい売れそうか、つまり「需要予測」を割り出して、無駄な在庫を減らすとか。
あるいは、工場の機械がいつごろ壊れそうか、「故障の予兆検知」を事前に行って、生産ラインが突然止まるのを防ぐとか。あとは、どういうお客さんがサービスを解約しそうか、「顧客離反の予測」を見つけ出して、先手を打ってフォローを入れるとか。
このように、何か問題が起きてから慌てて対応する、まあ「後手」の経営から、問題が起きる前に手を打つ「先手」の経営へとシフトしていくのを助けてくれる技術なんです。不確実な未来をデータに基づいて少しでも確からしく捉えて、より賢い判断を下すための、まあ「武器」と言えるかもしれません。
女性: 後手から先手へ、ですか。これは確かに経営にとっては大きな変化になりそうですね。これらの活用例を聞いていると、確かに中小企業のその限られた人員とか予算という課題、そして市場の変化への対応っていう点で、これは大きな助けになりそうだと感じます。
男性: ええ、その通りだと思います。例えば、生成AIを使って資料作成の時間が半分になったら、その浮いた時間をもっとお客さんへの対応とか、新しい企画を考える時間に充てられますよね。認識AIで検品作業を自動化できれば、少ない人数でも品質を維持しつつ生産性を上げられるかもしれない。予測AIで無駄な在庫をぐっと減らすことができれば、キャッシュフローだって改善します。
ここで大事なのは、ガイドが繰り返し推奨しているように、いきなり何か大きなシステムをドーンと導入するんじゃなくて、まずは課題がはっきりしている領域で小さく試してみることだと思うんです。
そして、あの、先ほども少し触れましたけど、画像認識AIでデータ化して、それを予測AIで分析して、その結果を生成AIで分かりやすい報告書にする、といったように、3つのAIをうまく組み合わせることで、さらに大きな効果が期待できる場合もあるわけです。あなたご自身のビジネスに照らしてみて、特に「あ、これはうちで使えるかも」と感じる活用法はどれかありましたか?
女性: うーん、そうですね、どれも魅力的ですけど、やはり日々の業務に直結しやすい認識AIでの効率化とか、あるいは予測AIを使った在庫の最適化あたりは、割とすぐにでも効果が出そうだなというふうに感じますね。
と、こう活用のイメージが具体的に湧いてくると、次に気になるのは、「じゃあ、どうやって始めればいいの?」っていうその疑問が出てきますよね。その最初の1歩について、ガイドはどういう風に示唆していますか?
男性: ええ、そこが一番皆さんが気になるところですよね。ガイドでは大きく分けて2つの始め方が示されています。
一つは**「ツール活用型」**というアプローチです。これは、まあChatGPTのような有名なものから他にも色々ありますけど、市販されているAIツールとかサービスをそのまま利用する方法ですね。比較的手軽に始められて、すぐに効果を実感しやすいというのがメリットです。
で、もう一つが**「システム開発型」**。これは、自社の例えば既存の業務システムなんかにAI機能を組み込んだり、あるいは全く独自のAIシステムを開発したりする、より本格的なアプローチになります。こちらはやはり、より高度な活用とか、他社には真似できないその独自の価値を生み出すことを目指す場合に考えられる選択肢ですね。
女性: ツール活用型とシステム開発型、なるほど。まあ、多くの中小企業にとっては、まずはツール活用型からっていうのが現実的な感じがしますよね。
男性: そうですね。多くの場合、そうなるだろうと思います。で、ここでガイドが提示しているのが、**「AI活用成熟度モデル」**という、ちょっと面白い考え方なんです。これは、自社がAI活用の今どの段階にいるのか、まあレベル0の無関心な状態からレベル5の最適化・革新の段階まであるんですが、それを客観的に把握するための、言わば「ものさし」ですね。
まず自分たちの会社の現在地を知って、無理なく段階的にステップアップしていくという考え方です。例えば、まずは無料の生成AIツールをちょっと試してみる(レベル1)。次に、有料のツールを導入して実際の業務に組み込んでみる(レベル2)。そして、ゆくゆくは自社のデータと連携させていく(レベル3へ)といった具合にですね。いきなりこうレベル5を目指すんじゃなくて、一歩一歩、着実に進んでいくことが重要だ、と。
女性: なるほど。自社のレベルを知って段階的に進む、と。それならなんか無理なく始められそうですね。ただ、まあこうした取り組みを進めていく上で、やはり経営者の意識とか、社内の体制づくりっていうのも重要になってきそうですよね。
男性: ええ、まさにその通りです。ガイドでも、AI導入が成功するかどうかっていうのは、経営者自身の強いリーダーシップ、つまりAIを自社の経営課題としてちゃんと捉えて推進していくぞというそのコミットメントが不可欠だ、とかなり強調されていますね。
そして、実際に社内で旗振り役となる、まあ「デジタル経営推進者」とガイドでは呼んでいますが、そういう担当者を明確にすることも非常に重要です。経営者がしっかりと方向性を示して、担当者が現場をうまく巻き込みながら具体的に進めていく、この両輪がうまく回ることが成功の鍵になるということです。
女性: リーダーシップと推進役、ですね。はい、覚えておきます。しかし、まあ良いことばかりじゃなくて、AIにはリスクもある、なんてこともよく聞きますよね。生成AIがなんか嘘をつくとか、情報漏洩が心配だとか、そのあたり、ガイドではどう触れられていますか?
男性: はい。リスクに関しても、ガイドはかなりしっかりとページを割いて解説しています。主なリスクとしては、今ご指摘があった通り、まず生成AIが事実に基づいていない情報、いわゆる「ハルシネーション」をもっともらしく生成してしまうという問題。
それから、機密情報とか個人情報をうっかりAIに入力してしまったことによる「情報漏洩」のリスク。AIが生成した文章とか画像が、気づかないうちに他人の著作権を侵害してしまう可能性。顧客データなんかを扱う際に、プライバシー侵害の問題。
そして、これも結構厄介なんですが、AIが特定の属性、例えば性別とか年齢とかに対して意図せず不公平な判断をしてしまう、「バイアス」の問題。こういったものが挙げられていますね。
女性: うわー、なんか聞いていると結構怖いですね。特にバイアスなんて、気づかないうちに何か差別的な判断とかしてしまったら大変なことになりそうですけど、これはどう対策すればいいんでしょうか?
男性: そこで重要になってくるのが**「リスクガバナンス」**という考え方なんです。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、要はですね、AIのリスクを単なる技術の問題として捉えるんじゃなくて、会社全体でちゃんと管理していく仕組みを作りましょうということなんです。
具体的には、まず「こういう目的で、こういうルールを守ってAIを使いましょうね」という社内のガイドラインを作成して、それを従業員にしっかり周知して教育すること。
次に、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策とか、個人情報の取り扱いに関するルールをきちんと徹底すること。外部のAIサービスを利用する場合は、契約内容、特にデータの取り扱いがどうなっているかをしっかり確認すること。
そして、先ほどのバイアスのような問題に対しては、AIが出してきた判断をそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、可能な範囲で「なぜAIがそういう判断をしたのか」を確認したり、最終的な判断は必ず人間が行う、いわゆる「ヒューマン・イン・ザ・ループ」というプロセスを組み込むこと。これらを計画的に行っていく必要があるということです。
女性: なるほど。ルールづくりと、あとは人のチェックが重要なんですね。ただ、まあ中小企業でそこまで手が回るかなっていうちょっと不安もありますけど。
男性: ええ、お気持ちはすごくよくわかります。だからこそ、ガイドでは「身の丈に合ったスコープ設定」っていうのが推奨されているんです。つまり、最初から全社的に、あるいは非常にリスクの高い業務でAIを使うんじゃなくて、まずは影響範囲が比較的小さい業務とか、リスクの低い領域から試してみるということです。
また、国とか関連団体が出している「AI事業者ガイドライン」みたいなものを参考にして、自社のルールを作るっていうのも有効な方法です。完璧を目指すというよりは、できることから着実にリスク対策を進めていくという姿勢が大切だと思います。
女性: 身の丈にあった対策から、ですか。うーん、それなら少し安心しました。そして、AI活用っていうのは、一度導入したら終わりっていうわけではないんですよね?
男性: ええ、そこもあの、非常に重要なポイントです。ガイドでは、AI活用というのは、「計画して」「開発・導入して」「活用・運用して」「評価・改善する」というこのサイクルを継続的に回していくものなんだと強調されています。
AIの技術自体も日進月歩で進化していますし、ビジネスを取り巻く環境も常に変化しますから、一度作って終わりではあっという間に古くなって使えなくなってしまいますからね。
女性: 計画、導入、活用、評価、改善。このサイクルをぐるぐる回し続ける、と。
男性: はい。この運用してみて、その効果をちゃんと測って、さらに良くしていくという反復的なアプローチ。実は、これ、IT導入を支援する専門家、つまりITコーディネータ協会が普段から使っている考え方、「プロセスガイドライン(略してPGL)」っていうのがあるんですが、その考え方にも通じるところがあるんです。
まあ別に、PGLという名前を覚える必要は全くなくてですね、大切なのは、この継続的な改善という考え方自体が、変化の激しいAIの時代にはもう不可欠なんだっていうことです。このサイクルをきちんと回していくことで、リスクをうまくコントロールしながら、AIから得られる価値を着実に高めていくことができるわけです。
女性: なるほど。そして、もし自社だけだとこのサイクルを回すのがちょっと難しいなということであれば、外部の専門家の力を借りるのも一つの手だ、と。
男性: ええ、その通りです。ガイドでも、ITコーディネータのような外部の専門家が、言わば「伴走者」として、客観的な視点とか専門知識を提供しながらAI活用の推進をサポートすることの有効性というのも述べられていますね。自社のリソースだけで全てを抱え込もうとせず、必要に応じて外部の知見をうまく活用するというのも賢い進め方の一つだと思います。
女性: よくわかりました。さて、今回の深掘り、そろそろまとめに入りましょうか。
まず、AI、特に生成AI、認識AI、予測AIという3つのタイプのAIは、もはや中小企業にとってどこか遠い話ではなくて、真正面から向き合うべき経営課題であるということでしたね。
次に、その活用は、あまり難しく考えすぎずに、具体的な業務改善のシナリオから、小さく試してみること。そして、自社の状況、まあ成熟度に合わせて段階的に進めていくこと。その際には、経営者のリーダーシップと社内の推進役の存在が鍵になるということ。
さらに、AIにはやはりリスクもあるということをちゃんと理解して、身の丈に合った対策を講じながら、継続的な改善サイクルを回していくこと。これが、今回のガイドから見えてきた、あなたがAIを自社の力に変えていくための重要なポイントでした。この情報が、あなたの何か次の1歩につながれば大変嬉しく思います。
男性: そうですね。最後に一つだけ、あなたの思考をちょっと刺激するような問いを投げかけさせていただけたらと思います。
ガイドの中ではですね、AI活用がさらに進んでいくと、中小企業がその会社ならではの独自のデータとかノウハウとAIを組み合わせることで、単なる業務効率化っていうのを超えて、まるでIT企業のように何か新しいサービスとか価値を生み出す存在に進化していく、そういう可能性についても触れられていたんですね。
効率化ももちろん非常に重要です。ですが、もしあなたの会社が持っている、他社には簡単に真似できないような独自の強み(それは長年培ってきた技術かもしれないし、あるいは地域との深いつながりかもしれない)、そういったものにAIを掛け合わせたとしたら、一体どんな全く新しい価値がそこから生まれる可能性があるでしょうか?
この問い、ぜひ一度持ち帰っていただいて、未来への想像を膨らませてみていただけたらと思います。
女性: いやー、面白い問いですね。効率化のその先にある、新しい価値創造の可能性。示唆に富むお話でした。本日はどうもありがとうございました。
男性: こちらこそありがとうございました。