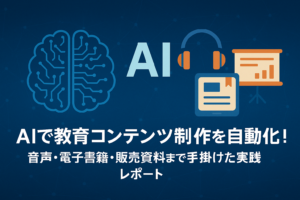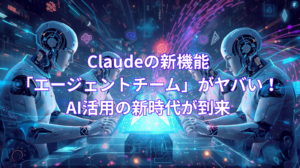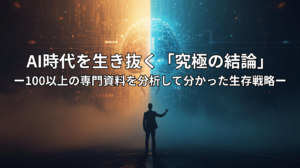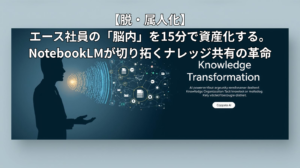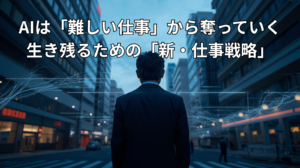こんにちは。今回は、AIを活用してオンライン講座のコンテンツを効率的に自動化する取り組みについてご紹介します。
講座コンテンツを一度作っただけでは終わりません。受講者の理解度を高め、移動中やスキマ時間でも学べるようにするには、音声化・電子書籍化・販促資料の整備が欠かせません。でも、これを全部人の手でやるのは大変すぎる……。
そこで私は、AI+Python+FFmpegなどのツールを使って、自動化に挑戦しました。
*FFmpeg(エフエフエムペグ)は、音声や動画の「変換」「編集」「録音」「ストリーミング」などを行える超高機能なマルチメディア処理ツールです。
オーディオブック作成もAIで一気通貫!
まず手をつけたのが、講義動画からのオーディオブック化です。
ただ音声を抽出するだけではありません。目指したのは「チャプター付きのM4B形式オーディオブック」。これがあれば、iPhoneの「Books」アプリで再生中に気になる章にすぐジャンプできます。
もともと私はPHPに慣れていたのですが、音声処理には向いていません。そこでPython+FFmpegに切り替えました。FFmpegは動画や音声処理の超強力なツールですが、コマンドがとにかく複雑で…今までは挫折していたんです。
しかし今は違います。ChatGPTなどの生成AIに、自然言語で「こういうプログラムを作って」と頼めば、数秒でサンプルコードが出てくる時代。おかげで短時間で自動化できました。
テキストブック(電子書籍)も自動生成!
次に取り組んだのは、講義内容を文章化して電子書籍にすること。
手作業ではものすごく時間がかかるこの作業も、AIの登場で一変。講義のスクリプトや内容を入力すれば、読みやすく整った文章が生成されます。
作成した形式は以下の通り:
- EPUB形式(iPhone/iPadの「Books」で閲覧)
- PDF形式
- Kindle向けMOBI形式
iCloudで同期しておけば、どこでも読めるし、Booksアプリのハイライト機能でメモも取れる。“読む講義”としての価値がぐんと高まります。
まとめ資料やランディングページも自動生成!
AI活用は音声や書籍だけではありません。以下のコンテンツもすべて自動生成しました:
- 要点だけを抜き出した「まとめ資料」:箇条書きで構成されたPDFやEPUBで提供。
- ランディングページ:講座の紹介文、特徴、受講者の声、よくある質問などもAIが下書きを作成。
- ステップメール:受講前のフォローメール10通
- サポート用メール:受講後のフォローアップ10通
- 関連ブログ記事:講座にまつわる10本の読み物コンテンツ
これらをすべて人力で作るとなると、少なくとも数週間〜1ヶ月は必要。でも、AIを使えば数日で完成します。
実際にどうやって自動化したのか?具体的な流れを紹介
では、どうやってこれらの自動化を実現したのか?ざっくりした手順はこんな感じです:
- 作業フローを設計 まず「人間だったらどうやるか」を紙に書き出します。
- 小さく分けて、順番に依頼 たとえば最初は「動画から音声を抽出するPythonスクリプト」をAIに依頼。 次に「抽出した音声をM4B形式に変換するスクリプト」。 このように小さく依頼するのがコツです。
- AIに自然言語で依頼 「フォルダの中のすべてのビデオから音声を抽出してください」と、人に頼むように指示。
- エラーが出たらそのまま報告 エラーメッセージをそのままコピーしてAIに見せれば、修正版のコードを提案してくれます。
- 最終的に統合プログラムを生成 分割されたスクリプトを1つの流れに統合して、ワンクリックで実行できるようにしました。
最も驚いたのは、これらの作業が2〜3日程度で実現できたこと。もちろんフルタイムではなく、空き時間で進めたにもかかわらずです。
AIで「人に伝える」ことを効率化する未来へ
これまで「文章を書くのが苦手」「動画編集なんて無理」と思っていた人でも、AIをうまく使えば、講座づくりが楽になります。
専門的なスキルがなくても、適切な指示を出すだけで
- 講義の音声化
- 講義内容の文章化
- 学習補助資料の作成
- 販売用ページやフォローアップの仕組み構築
が可能になります。
今後はこの仕組みをさらに応用して、たとえば習慣化をサポートする「メタルーピング」講座などの新しい分野にも展開していく予定です。
最後に
AIの進化は、教育現場にも確実に恩恵をもたらしつつあります。「人に届けるための準備」が、これほど短時間でできるようになった今、自分自身が教えることにもっと集中できるようになりました。
もしこの記事が、皆さんのこれからの講座設計やプロジェクトのヒントになれば嬉しいです!