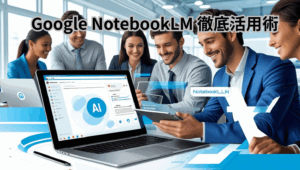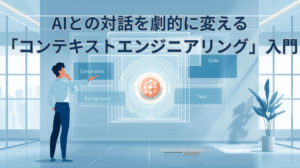PwC Japanグループが実施した「生成AIに関する実態調査2025 春」は、日本企業が生成AIの導入において、世界と比べてどのような現状にあるのかを深く掘り下げた興味深いレポートです。この調査は、売上高500億円以上の企業に勤務する課長職以上の方々を対象に、日本、米国、英国、ドイツ、中国の5カ国で実施されました。
調査結果から明らかになったのは、日本企業は生成AIの効率化や変革の可能性を認識しているものの、他国に比べてその効果を十分に引き出せていないという実態です。
日本は「活用は平均的」、しかし「効果は低水準」
グローバル比較を見ると、各国は生成AIの活用において異なる特徴を示しています。
- 米国・英国は、社外向けサービス活用で先行し、ユースケース展開や業務統合、ガバナンス態勢の整備においても他国をリードし、高い効果を上げています。これは比較的緩やかな規制環境と政府・産業界の支援に支えられています。
- 中国は、政府ガイドラインのもとで積極的かつ迅速に導入を進め、効果を上げつつ、多様なユースケースによるさらなる拡張を図っています。
- ドイツは、慎重な導入姿勢ながらも、効果的なユースケースを選定し、特に社外向けサービスに注力することで、米・英と同水準の効果を実現しています。
- 日本は、生成AIの導入度は平均的であるにもかかわらず、効果実感は他国に見劣りしています。特に「期待を上回る」効果を実感している企業の割合は、米・英の1/4、独・中の半分に留まっています。これは、生成AIが単なるツールとしての活用に留まっているためと考えられています。
この効果の格差は、時間の経過とともに指数関数的に拡大する傾向にあり、日本企業は早急な対応が求められています。
効果を上げる企業と上げられない企業の「二極化」が常態化
日本企業内でも、生成AI活用の成果には大きな「二極化」が見られます。効果を大きく上回る企業と、期待未満に終わる企業の間には、明確な分岐点が存在します。
成功する企業に共通する要因は、以下の点で突出しています。
- 高い目的意識と期待設定:生成AIを「業界構造を根本から変革するチャンス」と捉え、効率化だけでなく事業モデルの見直しを目指しています。
- 経営層の強力なリーダーシップ:
- 導入推進は「社長直轄」で行われる割合が非常に高く(期待を上回る層の61% vs. 期待未満層の8%)。
- CAIO(Chief AI Officer)の配置も進んでおり、AI活用推進の明確な責任者が存在します(期待を上回る層の60% vs. 期待未満層の11%)。
- 積極的な業務プロセス統合と投資:
- 生成AIが「業務プロセスの一部として正式に組み込まれている」と回答した割合が高く(期待を上回る層の72% vs. 期待未満層の14%)。
- 業務の「完全な置き換え」や「大部分の置き換え」を志向しており(期待を上回る層の70% vs. 期待未満層の16%)。
- 「全従業員が活用」する割合も高く(期待を上回る層の39% vs. 期待未満層の4%)。
- 数億円以上の大規模な予算を確保している企業も多いです(期待を上回る層の63% vs. 期待未満層の27%)。
- 強固な活用の土台(ガバナンス・情報収集・還元策):
- 最新技術に「十分にキャッチアップできている」と回答した割合が非常に高く(期待を上回る層の80% vs. 期待未満層の11%)。
- ガバナンス態勢やリスク対策が「十分に機能している」と回答した割合も高いです(期待を上回る層の77% vs. 期待未満層の19%)。
- 生成AIで生まれた効果を従業員への利益還元(給与増加、ボーナスなど)に「積極的」な企業が多いことも特徴です。
対照的に、効果が期待を下回る企業は、生成AIを単なるツールとして断片的に導入し、推進が現場任せになり、既存業務の延長線上での小規模改善に留まる傾向が見られます。
日本企業が直面する構造的課題と乗り越えるための提言
日本企業が生成AIの効果創出に遅れをとる背景には、日本特有の企業文化や意思決定スタイルが挙げられます。
- 合意形成重視・ボトムアップ志向:迅速で大胆なトップダウンの意思決定が難しい傾向があります。
- 失敗に対する過度な懸念:失敗がキャリアに影響すると考えられ、確実な小規模改善が優先されがちです。
- 低い目標設定と改善志向:「変革」や「再構築」といった高い目標が立てにくい傾向があります。
また、具体的な課題としては、人材不足(過半数の企業が直面)や「ノウハウがない」という回答が他国と比べて突出して高く、活用に対する不明瞭さが際立っています。さらに、生成AIが参照するデータが「社内業務データに偏りがち」であり、多様なデータの活用が進んでいない点も課題です。
これらの課題を乗り越え、生成AIの効果を最大化するために、レポートは以下の提言をしています。
- 正攻法による対応:
- トップダウンの戦略的意思決定と推進体制の整備:生成AIを「経営課題」と位置付け、CAIO配置やAI責任者の明確化を図る。
- 心理的安全性を備えた環境整備:挑戦を評価し、失敗を許容する文化を明示し、社内ベンチャーや外部連携なども活用する。
- 目標引き上げと変革マインドの醸成:変革を掲げたトップメッセージを発信し、中長期の戦略的目標を明確にする。
- 日本の特性を活かした対応:
- 現場力・改善文化の活用:日々の改善サイクルがAIエージェントやロボットの現場適応を高速化する源泉となる。
- 少子高齢化への対応:労働力不足という社会課題に対する強い需要が、生成AI活用の原動力となる。
- ロボット・AI親和性:「相棒」としてAIやロボットを受け入れる文化を活かす。
- 新技術への受容性:「まず試す」文化が、技術の精度向上から実運用までの原動力となる。
- 標準化・横展開力:個人や部門の成功事例を全社・社会的なベストプラクティスとして迅速に共有・展開する。
日本企業が生成AIを単なる効率化のツールではなく、ビジネス変革の中核と再定義し、高い目標設定、革新文化の醸成、ビジネスモデルの再構築に取り組むことが、グローバル競争での活路を切り開く鍵となるでしょう。