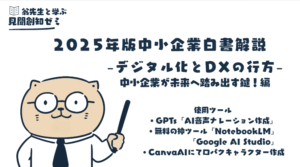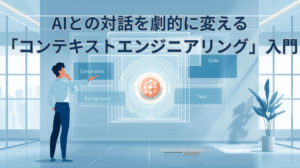2025年版中小企業白書・小規模企業白書が発表され、今年の大きなテーマは「中小企業の経営力」の向上と「スケールアップへの挑戦」であるとされています。円安・物価高の継続、金利のある世界への移行による生産・投資コストの増加、構造的な人手不足など、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。このような激変する環境を乗り越え、成長と発展を実現するためには、自社の現状を把握し、適切な対策を打つ「経営力」が不可欠です。
この中で、特に注目されているのがデジタル化とDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用です。
デジタル化とDX、その違いとは?
まず、「デジタル化」と「DX」は混同されがちですが、これらは異なる段階の取り組みです。
- デジタル化は、紙や口頭で行っていた業務をデジタルツールに置き換えるなど、アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境へ移行することを指します。
- これに対し、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、「顧客視点で新たな価値を創出していくために、ビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むこと」を指します。つまり、単にデジタルツールを使うだけでなく、デジタル技術を活用して事業のあり方そのものを変革することを意味します。
中小企業におけるデジタル化とDXの現状
白書のデータを見ると、中小企業のデジタル化は一定の進展を見せています。
- 2023年から2024年にかけて、「紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態」(段階1)と回答する事業者の割合が大きく減少し、2024年には12.5%となりました。これは、最低限のデジタル化が進んでいることを示唆しています。
- しかし、一方で「デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態」(段階4、すなわちDX)と自信を持って回答できる事業者の割合は、依然として限定的であり、数値的には減少している部分も見られます(調査の母集団の違いには留意が必要)。
企業の規模別に見ると、デジタル化の進捗状況には差があります。
- 一般的に、企業規模が大きいほどデジタル化が進んでいる傾向にあります。例えば、年商100億円規模の企業では、段階1の「アナログ企業」はほとんど見られませんが、それでもDX(段階4)に取り組む企業の割合はわずかです。
- 具体的な取り組み内容では、コミュニケーションツールの導入やセキュリティ対策は規模が大きい企業ほど進んでいます。また、営業活動や受発注管理のオンライン化、バックオフィスでのクラウドサービス活用も、規模の大きい企業の方が高い割合で進められています。
- しかし、AIやRPAといった最新のIT技術の活用は、まだどの規模の企業でも数パーセントから十数パーセント程度に留まっており、今後の大きな成長余地があると言えるでしょう。
DX推進の課題
DXを進める上での主要な問題点としては、以下の点が挙げられています。
- 費用の負担が大きい
- DXを推進する人材が足りない
- どのように推進すればよいか分からない
- 具体的な効果や成果が見えない
これらの課題は、デジタル化の取り組み段階に関わらず、多くの事業者で共通しています。
スケールアップとDXの密接な関係
白書では、売上高100億円規模を目指す「100億企業」の育成を重要なテーマとして掲げており、このスケールアップにおいてDXが不可欠であると強調しています。
- 特に売上高10億円未満の企業にとっては、経営者が一人で全てを管理する限界が「成長の壁」となりがちです。この壁を克服し、規模を拡大するためには、経営者に足りないスキルを補う専門人材の確保や、職務権限の委譲が必要とされており、DXによる業務変革を主導できる人材の重要性が高まっています。
DX成功事例に学ぶ「身の丈DX」と変革の力
厳しい環境下でも攻めの経営で成果を出している企業の事例が紹介されています。
- 株式会社倉岡紙工(熊本県)は、「暗い・きつい・汚い・危険」という「4K職場」からの脱却を目指し、「身の丈DX」を推進しました。約3,000個もの木型の管理にIoTを導入し、探す時間をゼロに。さらに梱包作業の機械化などで従業員の負担を大幅に削減した結果、顧客数は20社から100社超に、従業員数は倍増し、新規受注も獲得しています。これは、限られたリソースの中で従業員の負担を取り除くことに焦点を当てたDXが、業績向上と人材確保の好循環を生み出した好例です。
- 株式会社広島メタルワーク(広島県)は、他の中小企業8社と共同で安価な生産管理ソフト「TED」を開発・導入しました。これにより、社員一人当たりの売上高が8.6%増加し、労働時間は15.9%削減、さらには不良率を97%も削減するという驚異的な成果を上げています。同社の前田社長は、「今の会社の仕組みに合わせてデジタル化を進めるのではなく、既存のデジタルツールに合わせて仕組みを変えていくこと」が重要だと語っています。
- マツモトプレシジョン株式会社(福島県)は、事業承継を機にDXとGX(グリーントランスフォーメーション)に大胆に取り組みました。製造原価のデータベース化、低採算事業の半減、約50台の省力化設備への刷新、タブレットによる作業進捗管理などを実施。その結果、利益率は3割近く向上し、全従業員を対象に4%のベースアップを実現しました。賃上げという明確な目的が、全社一丸での変革を可能にしました。
これらの事例は、DXが単なるコストではなく、**従業員のやる気向上や新たな事業機会の創出、ひいては企業の成長と持続的な賃上げへとつながる「未来への投資」であることを示唆しています。
国の支援策
政府も中小企業のデジタル化・DXを力強く後押ししています。
- IT導入補助金や省力化投資補助金など、デジタルツールや省力化投資に対する補助金が用意されています。
- 「新規輸出1万者支援プログラム」のように、海外展開を目指す企業への戦略立案、マッチング、直接輸出の支援も行われています。
- 事業承継を支援する税制(事業承継税制)や、M&A後の経営統合(PMI)を支援する「PMI推進枠」のある補助金など、攻めの経営をサポートする様々な制度が提供されています。
まとめ
中小企業が直面する厳しい経営環境において、デジタル化とDXは単なる「生き残り策」ではなく、「攻めの経営」を実現し、企業価値を高め、持続的な成長を実現するための重要な戦略です。経営者が自らDXをリードし、自社の状況に合わせた「身の丈DX」から始め、生産性向上やビジネスモデル変革に取り組むことで、利益を増やし、従業員への還元、ひいては新たな事業機会の創出へとつながる好循環を生み出すことが期待されます。
この白書が、中小企業・小規模事業者はもちろん、地方公共団体や支援機関等の幅広い方々に発見をもたらすことを期待しています。政府としても引き続き、賃上げ原資の確保に向けたサプライチェーン全体での価格転嫁の定着や、「稼ぐ力」の向上に向けた生産性向上支援といった対策に全力で取り組んでいくとのことです。
(執筆:中小企業デジタル経営支援アドバイザー 辻本泰雄)
耳聞創知:サクっと要点把握に
「耳聞創知(じぶんそうち)」とは、人から聞いた知識(耳聞)をもとに、自らの思考によって新たな理解や知恵(創知)を生み出すことを意味する言葉です。気軽に活用してください!