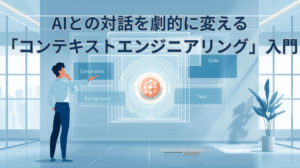「会議で何かアイデアを出してと言われても、いつも似たようなことしか思いつかない…」
「画期的な企画を考えたいのに、思考がずっと同じところを堂々巡りしてしまう…」
もしあなたがそんな風に自分の発想力に限界を感じているなら、ご安心ください。それは、あなたの才能や努力が足りないせいではありません。実は、私たち人間の「脳の仕様」そのものに原因があるのです。
この記事では、私たちの思考がなぜ固まってしまうのかを科学的に解き明かし、その思考の壁をAIの力で強制的に破壊する「禁断のプロンプト術」を具体的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたのアイデア発想法は、昨日までとは全く違う次元にアップデートされているはずです。
1. なぜ私たちのアイデアは行き詰まるのか?脳に隠された「思考の癖」
そもそも、なぜ私たちの思考は同じような場所をぐるぐると回ってしまうのでしょうか。それには、脳が持つ2つの厄介な癖が関係しています。
無意識に同じ“山”を登ろうとする脳
アイデア出しはよく「登山」に例えられます。一度、あるルートで登頂に成功すると、次に別の山を登るときも、無意識に「前に成功したあのルートと似た方法」を選んでしまいがちです。これが、新しい企画を考えているはずなのに、気づけば過去の成功パターンをなぞっただけのアイデアになってしまう原因です。
科学的根拠①:脳の無意識な「省エネ機能」
この現象は、脳がエネルギーを節約するために生まれつき備えている「省エネ機能」が原因です。ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンが提唱する「利用可能性ヒューリスティック」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、「思い出しやすい情報や成功体験に無意識に頼ってしまう」という、人間の思考のショートカット機能のことです。脳は楽をしたいので、わざわざ新しい大変な道を探すより、一度うまくいった簡単な道を選んでしまうのです。
科学的根拠②:集中するほど視野が狭まる「思考の固定化」
さらに、オランダのライデン大学の研究では、脳の短期記憶(ワーキングメモリ)が活発な状態、つまり「一つのことにぐっと集中している時」ほど、かえって思考が一点に固まってしまう「思考の固定化」が起きやすいことが示唆されています。皮肉なことに、私たちは「良いアイデアを出そう!」と一生懸命考えれば考えるほど、無意識のうちに視野が狭まり、同じ場所をぐるぐる回り続けてしまうのです。
2. 思考の限界を突破する鍵はAIにあり
では、脳の仕様に組み込まれた「思考の固定化」という壁を、どうすれば乗り越えられるのでしょうか?ここで登場するのがAIです。
人間は、「広くたくさんの選択肢を探すこと」と「決めた一つの道を深く掘り下げること」を同時に行うのが非常に苦手です。マルチタスクが苦手なのは、脳の構造上仕方のないことなのです。
しかし、AIはそれを難なくこなします。
AIは、私たちが今いる思考の地点から、全く別のアイデアの麓まで一瞬で連れて行ってくれる、まさに「思考のどこでもドア」のような存在です。AIを思考のパートナーとして正しく使うことで、私たちは自分自身の脳が持つ限界すら、軽々と超えることができるのです。
3. 実践!思考を強制ワープさせる「禁断のプロンプト術」
AIという「どこでもドア」を使うために必要なのが、行き先を正しく指示する「ワープポイント」です。それが、これからご紹介する「6つの観点」を用いたプロンプト術です。
アイデアを多角化する「6つの観点」
これは、5W1Hをアイデア発想用にさらに強力に進化させた、想像工学の研究者たちが築き上げてきたフレームワークです。この6つの視点から強制的に物事を捉え直すことで、思考の固定化を破壊します。
- 人:関わる人々、その立場、能力、顧客
- 物:製品、素材、サービス、人以外の生き物
- プロセス:人と物の動き、手順、相互作用、体験の流れ
- 環境:場所、時間、状況、市場、風土
- 意味・価値:目的、コンセプト、感覚的な価値、ゴール
- 五感:見た目、音、手触り、香り、味など感覚的な視点
【実践例】AIに「売上が伸び悩むカフェ」の集客アイデアを出してもらう
この6つの観点を使い、実際にAIにアイデアを出してもらいましょう。ポイントは、各観点の具体例をあえてプロンプトにごちゃごちゃと列挙することです。これにより、AIの思考を刺激し、安定して多様なアイデアを引き出せます。
▼コピペで使える!禁断のプロンプト例 code Codedownloadcontent_copyexpand_less
#テーマ
売上が伸び悩むカフェの新しい集客アイデア
#指示
上記のテーマについて、下記の6つの観点から多様なアイデアを網羅的に生成してください。
–五感(例:内装デザインの刷新、BGMの選定、コーヒーの香り、座り心地の良い椅子、ラテアートの美しさ)
–人(例:ターゲット客の再設定、スタッフの魅力向上、インフルエンサーとの協業、地域住民との連携)
–物(例:看板メニューの開発、限定グッズの物販、こだわりのコーヒー豆のサブスク、インスタ映えする食器)
–プロセス(例:注文・決済方法の多様化、モバイルオーダーの導入、顧客体験の向上、スタンプカードのデジタル化)
–環境(例:店舗空間の魅力向上、リモートワーク向けスペースの設置、立地の活用、オンラインイベントの開催)
–意味・価値(例:コンセプトの再定義、店のストーリー発信、社会貢献活動との連携、”サードプレイス”としての価値提供)
▼AIの回答(要約)
このプロンプトをAI(GeminiやChatGPTなど)に投げると、各観点から網羅的にアイデアが生成されます。「人」なら学生向けの新プラン、「物」なら季節限定のドリンク開発、「プロセス」なら体験型ワークショップの開催など、人間一人では思いつくのに時間がかかる、あるいは抜け漏れがちな視点を一瞬で洗い出してくれます。
私たちは、AIが出してくれたこの膨大なアイデアリストを眺め、面白そうなものを深掘りしたり、異なる観点のアイデアを組み合わせたりすることで、これまでたどり着けなかった革新的な企画へと昇華させることができるのです。
まとめ
今回は、アイデアの枯渇を乗り越えるためのAI活用術について解説しました。最後に、今日のポイントをまとめます。
- 私たちの脳は、効率化のために無意識に思考を固定化させてしまう仕様になっている。
- AIと「6つの観点」を使えば、その脳の仕様をハッキングし、思考を強制的にワープさせることができる。
- AIが出した多様なアイデアを元に、人間がさらに深掘りすることで、思考の限界を超えることができる。
これからの時代、「AIに使われる」のではなく「AIを使い倒す」というマインドセットが、あなたのビジネスやキャリアを大きく左右します。
ちなみに、今回ご紹介した「6つの観点」という技法は、『AIを使って考えるための全技術』という書籍でさらに詳しく解説されています。AIと共に思考を拡張するためのテクニックが満載ですので、ご興味のある方はぜひ手に取ってみてください。
まずは今日のプロンプトを参考に、あなたが抱えている課題をAIに投げかけることから始めてみましょう。きっと、驚くような発見が待っているはずです。
参考プロンプト(禁断のプロンプト):技法8:代表的な6つの観点に着目してアイデアを発掘方法!
代表的な6つの観点に着目してアイデアを発想します。 AIへの指示文(プロンプト) 広くアイデアを出すには以下に示す6観点が役立ちます。カッコ内は観点の詳細です。これらを参考にして、〈 アイデアを得たい対象を記入 〉について多様なアイデアを生成してください。→人(主体、客体、単数、複数、立場、能力、市場、仕入れ先)、モノ(製品、素材、人以外の生き物)、プロセス(人とモノの動き、役割、相互作用)、環境(風土、取り巻く場、状況、時間、空間、構造)、意味・価値(意味、価値、感性、感情、金、情報、強み、機会、ビジョン、ゴール)、五感で感じるもの(色・形、音、におい、味、質感、触感、食感)
(コピペして〈〉の中身をあなたのテーマに変えるだけで使えます)
参考書籍
このブログで解説した内容は、書籍『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている50以上のテクニックのうちの1つです。もっとずるい思考法を知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
・AIを使って考えるための全技術