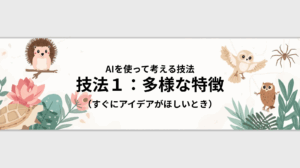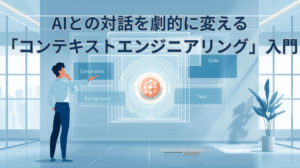「新しい企画のアイデアが思いつかない…」
「一人で考えても、ありきたりな案しか出てこない…」
ビジネスパーソンなら誰しもが抱えるアイデア出しの悩み。もし、その悩みを解決し、あなたの思考を何倍にも拡張してくれるパートナーがいたらどうでしょうか?
今やAIは、単なる作業の効率化ツールではありません。私たちの創造性を刺激し、思考の壁を打ち破るための強力な「相棒」となり得ます。
この記事では、話題の「AIを使って考えるための全技術」の中から、特に効果的で今日からすぐに実践できる5つの画期的な発想法を厳選してご紹介します。AIとの対話を通じて、あなたの中に眠る革新的なアイデアを引き出しましょう。
1. 仮想ブレストチームを即結成!「各種専門家の案」
ブレインストーミングで多様な意見が欲しい時、外部の専門家を呼ぶのは理想的ですが、守秘義務や費用、スケジュールの問題で実現は困難です。しかし、AIを使えば、この課題を瞬時に解決できます。
この手法は、AIに様々な専門家の役割(ペルソナ)を与え、あなたのテーマについて多角的な視点からアイデアを出してもらうというものです。
【使い方】
AIに対して、以下のような役割になりきってもらうよう指示します。
- クリエイティブの専門家: 斬新で美しいアイデアを提案
- ディスラプター(破壊者): 業界の常識を覆す過激なアイデアを提案
- 社会学者: 社会的な背景や人間行動からアイデアを考察
- ユーモアのセンスを持つ人: 人々を笑顔にするユニークなアイデアを提案
- 冒険者: 前例のない、大胆で挑戦的なアイデアを提案
これにより、自分一人では決して生まれなかったような、多彩な観点からのアイデアが次々と湧き出してきます。まるで、世界中の専門家を集めた豪華なブレストを、深夜一人でも、いつでも好きな時に開催できるのです。
2. 思考の限界を突破させる「10倍の目標」
AIに質問しても、無難で妥当な答えしか返ってこなくてがっかりした経験はありませんか?AIも、常識的な問いかけには常識的な範囲で答えがちです。そんなAIの(そして自分自身の)思考の枠を壊すのが「10倍の目標」というテクニックです。
やり方は至ってシンプル。「50cmの壁を越えたい」という目標なら、「5mの壁を人力で越えたい」というように、あえて非現実的なほど高い目標をAIに設定するのです。
【使い方】
- 本来の目標を、AIに10倍のスケールで課題として与える。
- AIは、正攻法では達成不可能なため、トリッキーで突飛なアプローチを考え出す。
- 出てきた斬新なアイデアリストの中から、ヒントになる要素を抜き出す。
- そのヒントを、本来の目標に合わせて現実的な企画に落とし込む。
この「無茶ぶり」によって、AIは思考のリミッターを外し、驚くような発想を提示してくれます。アイデアがマンネリ化し、「何か跳ねないな」と感じた時にこそ試してほしい、強力な起爆剤です。
3. 芸術的センスをインストールする「アートの示唆」
ロジカルに考え抜くだけでは、人の心を動かすような豊かなアイデアは生まれません。時には、芸術作品に触れて感性を刺激することも重要です。この「アートの示唆」は、そのプロセスをAIで再現するメソッドです。
ゴッホの『星月夜』、岡本太郎の『太陽の塔』…。歴史的なアート作品には、見る者を惹きつける創造的なエッセンスが凝縮されています。この手法では、AIにそうした作品のエッセンスを抽出させ、あなたのビジネス課題と掛け合わせてもらうのです。
【使い方】
AIに「ゴッホの『星月夜』が持つ情熱的で幻想的なエッセンスを、新商品のお菓子のコンセプトに応用するアイデアを出してください」といった形で依頼します。
すると、ビジネスの文脈だけでは生まれ得なかった、情緒的で魅力的なコンセプトや、意外な切り口のアイデアが生まれます。企画に新しい風を吹き込み、深みと豊かさを与えたい時に、ぜひ活用してみてください。
4. 根拠ある未来を導き出す「先見倍歴(せんけんばいれき)」
新規事業やプロダクト開発において、未来を予測し、説得力のあるアイデアを立てることは不可欠です。そこで役立つのが、イノベーション理論「TRIZ」をベースにした「先見倍歴」という思考法です。
これは、「10年後の未来を知りたければ、その倍の20年前に遡りなさい」という考え方に基づきます。過去20年間の技術や社会、ライフスタイルの変化の「変化量」を分析し、その同じ分だけ未来が変化すると仮定することで、極めて合理性の高い未来像を描き出すのです。
【使い方】
この手法は以下のステップを踏みますが、AIを使えば一括で実行できます。
- テーマ設定: 「10年後の自転車」など。
- 過去の分析: AIに20年前の自転車の部品、技術、社会環境などを分析させる。
- 変化量の算出: 20年前と現在を比較し、進化した要素・変化した要素を特定する。
- 未来予測: その変化量と同じ分だけ、現在の状況から10年後が進化・変化すると仮定し、未来の部品やライフスタイルを予測させる。
- アイデア創出: 予測された未来環境にふさわしい「10年後の自転車」のアイデアをAIに出力させる。
このステップの長い思考法も、AIなら一瞬です。エンジニアリング分野はもちろん、サービスや事業戦略など、説明責任が求められる場面で絶大な効果を発揮します。
5. 日常が宝の山に変わる「写真の中のヒント」
アイデアの種は、意外とあなたの日常に眠っています。スマートフォンのフォルダに溜まっている何気ない写真が、その起爆剤になります。
この手法は、あなたが撮った写真をAIに読み込ませ、そこに写っているものをヒントにアイデアを出してもらうという、非常にシンプルかつクリエイティブな方法です。
【使い方】
- アイデア出しに行き詰まったら、スマホのフォルダを開く。
- 旅行先の風景、道端で見つけた不思議な置物、美味しそうな料理など、気になる写真を一枚選ぶ。
- ChatGPTなどの画像認識が可能なAIにその写真をアップロードする。
- 「この写真からヒントを得て、〇〇(あなたのテーマ)に関する新しいアイデアを出してください」と依頼する。
AIは、あなたが意識していなかったような写真の細部(色、形、写り込んでいる人々など)を読み取り、テーマと掛け合わせることで、予期せぬアイデアを生み出してくれます。ビジュアルを使うので直感的で楽しく、AI導入に抵抗があるチームメンバーを巻き込む最初の一歩としても最適です。
まとめ
今回ご紹介した5つの手法は、AIを単なる検索エンジンではなく、あなたの思考を拡張する「創造的パートナー」へと変えるための具体的な鍵です。
- 各種専門家の案: 多角的な視点を瞬時に得る
- 10倍の目標: 思考の限界を突破する
- アートの示唆: 企画に豊かさと意外性を加える
- 先見倍歴: 合理的で説得力のある未来を描く
- 写真の中のヒント: 日常をアイデアの源泉に変える
AIとの対話は、まさに知性の壁打ちです。難しく考えずに、まずは一つ、気になった手法から試してみてください。きっと、これまで出会えなかったような、刺激的で新しいアイデアの世界が拓けるはずです。
参考プロンプト
技法5:「各種専門家の案」
多数の専門家(クリエイティブな専門家、技術専門家、ビジネス専門家、学術研究者、社会科学者、ユーザー、ディスラプター、ユーモアのセンスを持つ人々、冒険家)として< アイデアを得たい対象を記入 >について具体的な案を考えてください。
技法2:「10倍の目標」
本来の発想のお題< 課題や目標を記入 >に含まれる目標を10倍高い目標にしたお題を生成してください。次にその目標が実現している状態を7つ連想してください。最後に各々の状態を切り口にして、「本来の発想のお題」について「魅力的で、実行しやすいアイデア」を提案してください。
技法4:「アートの示唆」
< 課題を記入 > このお題に関して、有名な小説や絵画から得られる創造的なアイデアは何ですか?
技法16:「先見倍歴」
「先見倍歴」という未来予測の方法を定義します。 ①対象(「製品」または「事業」)を取り巻く現時点の「社会環境」と「技術要素」について列挙します。 ②それら(「環境要素」と「技術要素」)の過去30年の変化を洗い出します。 ③その変化分と同じだけ、現在の時点から発展させたら、それら(社会環境や技術要素)はどのぐらい変わるか、を推定します。 ④過去30年の変化分は、未来の15年間の変化分に相当すると仮定します。未来(15年後)に対象を取り巻く「社会環境」や「技術環境」をもとに、未来の対象(「製品」または「事業」)の姿を構想します。 この「先見倍歴」を用いて< アイデアを得たい対象を記入 >の15年後の姿を予測してください。 ※「15年後」を予測する場合を書いています。状況に応じて書き換えてください
技法11:「写真の中のヒント」
この画像から思い浮かぶことを10個あげてください。次にそれを材料にして< アイデアを得たい対象を記入 >として妥当なものを3つ、意外なものを3つ考案してください。
※画像を添付した上で使ってください
参考書籍
解説した内容は、書籍『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている50以上のテクニックのうちの5つです。もっとずるい思考法を知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
👉『AIを使って考えるための全技術』