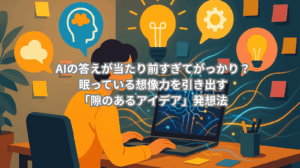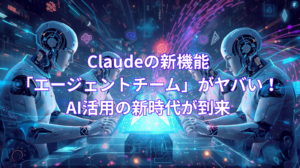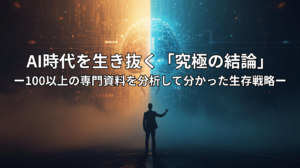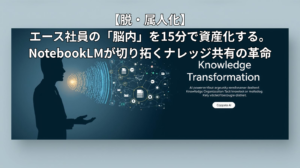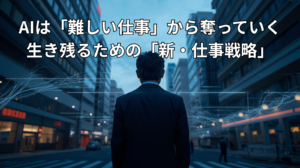AIにアイデアを出させても「当たり前の答えしか返ってこない」と感じたことはありませんか?この記事では、ピカソやゴッホのアート思考をAIに応用して、日常やビジネスで誰も思いつかない創造的アイデアを引き出す方法を具体例とともに解説します。
正論ばかりのアイデアで行き詰まっていませんか?
ロジカルシンキングを学んで真面目に企画を考えても、出てくるのは「そりゃそうだよね」という正論ばかり。間違ってはいないけれど、面白くも斬新でもない。そんな経験はありませんか?
実は、私たちが普段使う論理的思考には、明確な限界があります。既存の枠組みや改善策を考えるのは得意でも、ゼロから新しいものを生み出すことは苦手なのです。
ロジック思考だけでは光らない理由
例えば、ロウソクをどれだけ効率よく改良しても、電球を発明することはできません。改良(既存の改善)と発明(新しい価値創造)の間には、思考の大きなジャンプが必要なのです。
このジャンプを助けてくれるのが、今回紹介する「アートの示唆」という技法です。
AIを使った「アート思考」のすすめ
「アートの示唆」とは、ビジネス課題を優秀な会計士ではなく、天才的な詩人や画家に相談するようなイメージです。異なる視点から私たちが思いつかない答えを引き出してくれるのです。
優れたアート作品には、人の心を揺さぶる構造や物事の本質を捉えるメタファーが隠されています。AIにそのエッセンスを抽出させ、課題に応用することで、従来の思考の枠を飛び越えたアイデアが生まれます。
実践:硬い課題もアートで溶かす
例として、非常に硬いお題「国民全員が納得する日本国憲法の改正案」に挑戦してみます。
普通に考えれば不可能ですが、AIにアートの視点を与えることで、思いもよらない方向のアイデアが出てきます。
- 小説からの発想
ジョージ・オーウェル『1984』やヴィクトル・ユーゴー『レ・ミゼラブル』などの作品から、情報自己決定権や社会的孤立から尊厳を守る権利、生存権の強化といった視点を抽出。 - 絵画からの発想
ピカソ『ゲルニカ』からは、非軍事的な国際貢献や政策形成への国民参加の新設。浮世絵からは環境権や将来世代への責任、防災対策を憲法に組み込むアイデア。
こうして、AIが提示する「普遍的で人間的な価値観」に基づくアイデアは、特定の政治的立場に偏ることなく、理想の社会像を描くための素材となります。
プロの技:AIプロンプトの改造
さらに、AIに与えるプロンプトを少し改造すると、より柔軟で独自性のあるアイデアが出せます。
例えば、「有名な小説や絵画」を「日本の浮世絵」に変えるだけで、アートの作品を絞り込むことができ、思考の幅が広がります。
注意点:ハルシネーションに気をつける
AIは固有名詞や事実を平気で嘘として出力することがあります(ハルシネーション)。
たとえば、「ゲルニカのテーマはこうだ」とAIが言った場合でも、必ず自分で確認することが重要です。ファクトチェックを忘れずに行いましょう。
アート思考の副産物
この技法を使い始めると、美術館での作品鑑賞も変わります。「この絵の構造を仕事に応用できないか」「この色彩の配置は新しい企画に活かせるか」と、今までとは異なる視点でアートを楽しめるようになります。
まとめ:正論思考からの脱却
今回のポイントは次の4つです。
- 論理的思考で行き詰まったらアートの力を借りる。
- AIに有名な小説や絵画から発想させて、斬新なアイデアを引き出す。
- プロンプト内の「有名な」という部分を改造して、自分だけの視点を作る。
- AIが出す固有名詞はハルシネーションの可能性を疑い、必ず確認する。
あなたも正論だけでアイデアが出ない課題を抱えているなら、ぜひこの「アート思考」を試してみてください。AIと一緒に、ピカソやゴッホの視点を借りた感性的なアイデアを生み出す体験は、思考の幅を劇的に広げてくれるはずです。
参考プロンプト(技法4)
〈 課題を記入 〉
このお題に関して、有名な小説や絵画から得られる創造的なアイデアは何ですか?(コピペして〈〉の中身をあなたのテーマに変えるだけで使えます)