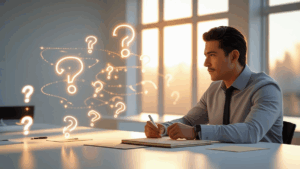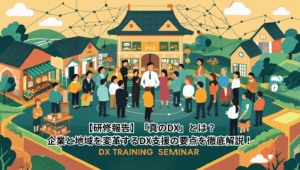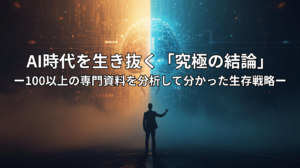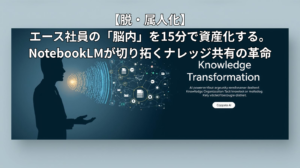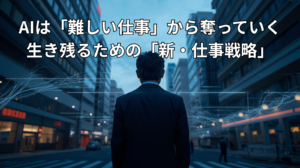皆さん、学生時代は教科書に載っている「正解」を見つけることで評価されてきましたよね?しかし、社会に出るとどうでしょう。競合他社との差別化や新商品の開発など、「正解のない問題」に直面する毎日ではないでしょうか?
実は、学校で優秀だった人が社会に出ても必ずしも活躍できるとは限らないのは、この「正解のない世界」に戸惑ってしまうからかもしれません。
そんな時代を生き抜き、成果を出すために今、あなたに最も必要な力。それは、「問いを立てる能力」だと、今回ご紹介する書籍『今、あなたに必要なのは答えじゃない。問いの力だ。』の著者は語っています。
答えを探し続けても、世の中に「答え」が落ちているわけではありません。自分で「問い」を立て、自分で「答え」を見つけるしかないのです。そして、良い問いを立てられれば、もはや成果の半分以上は達成したようなものだとまで言われています。
では、一体「良い問い」とは何なのでしょうか?そして、「悪い問い」とは?具体的な例を交えながら解説していきます。
成果を阻む「悪い問い」とは?
まず、避けるべき「悪い問い」から見ていきましょう。悪い問いは、問題解決につながらないだけでなく、人間関係を悪化させたり、相手を落ち込ませたりする可能性もあります。
その代表例が「なぜ?」という問いです。
例:「なぜ失敗したの?」 あなたが仕事でミスをした時、上司から「なぜ失敗したの?」と聞かれたら、どう感じるでしょうか?多くの人は、つい「いや、でも…」と弁明したくなるのではないでしょうか。これは人間が持つ「自己防衛本能」によるものです。責められていると感じると、自分を守るために言い訳を考えてしまうのです。
このような、相手の言い訳を引き出してしまう「なぜ?」という問いは、良い問いとは言えません。もし使うのであれば、自己防衛本能を刺激しないような工夫が必要になります。
成果に直結する「良い問い」とは?
では、反対に「良い問い」とはどのようなものでしょうか? 良い問いは、問題解決に直結するものです。著者の師匠でもある世界的ベストセラー『ザ・ゴール』の著者、ゴールドラット博士は、「問題を正確に定義しなさい。そうすれば問題は半分解決したも同然だ」と常に言っていたそうです。
問題とは、「現状と目標のギャップ」のこと。良い問いは、このギャップを明確にする問いなのです。
具体的な良い問いの例:
- 望ましくない現象は何ですか? (現状を明らかにする問い)
- 望ましい現象は何ですか? (目標を明らかにする問い)
この2つの問いを立てて自ら答えることで、問題が正しく把握され、解決へとつながっていきます。
【要注意】「目標」と「手段」を混同していませんか?
良い問いを立てる上で特に注意が必要なのが、目標と手段を履き違えてしまうことです。
例:社員の危機感がないと嘆くマネージャー あるマネージャーが「社員に危機感がない」と嘆いていたとします。
- 望ましくない現象:社員に危機感がない。
- では、望ましい現象は?:「社員が危機感を持つこと」だと考えていませんか?
実は、これは間違いです。社員が危機感を持つことは、あくまで**「手段」であって「目標」ではありません**。
なぜ社員に危機感を持ってほしいのでしょうか?そこを深く掘り下げてみましょう。もしかしたら、「社員の皆が高い目標に向かって生き生きと働いている状態を作りたい」というのが本当の目標かもしれません。
しかし、もし目標が「社員が生き生きと働くこと」であるならば、「危機感を持たせる」という手段は逆効果になる可能性もあります。危機感ばかりでは、社員はピリピリしてしまい、生き生きとは働けないでしょう。
このように、本当の目標を明確にしないまま問いを立てると、真逆の方向に進んでしまうこともあります。良い問いは、未来の「どういう状態になったら良いか」という目標がしっかりと設定されているものなのです。
問いを立てて「待つ」という究極の極意
この「問いの力」を最大限に引き出すための極意が、著者の体験談から語られています。
よくある職場のお悩み: 「指示待ち人間が多い」「言われたことしかやらない」「人が育たない」。
こうした現場には、往々にして「敏腕マネージャー」がいることが多いそうです。彼らは部下の話を聞き終える前に次々と指示を出します。一見、的確な指示のように聞こえますが、実態は「答え」を教えてしまっているのです。
これでは、部下は自分で考える必要がなくなり、責任感も育ちません。結果として、「指示待ち人間」が増えてしまうのです。これは、先にゴールドラット博士が言っていた「答えを教えることが学ぶことの最大の障害」という言葉そのものです。
敏腕マネージャーの変革: 著者はこの敏腕マネージャーに、先に解説した「良い問い」を投げかけました。 「望ましい現象は何ですか?」(=目標は何ですか?)
するとマネージャーから返ってきた答えは、「自分で問題解決できる人材を育てたい」でした。
この明確な目標を持ったマネージャーは、現場の社員たちに対し、次のような問いを投げかけるようになりました。
「何か助けられることはないですか?」
一見、優しい問いかけに聞こえますが、実はこれは非常に厳しい質問です。この問いを投げかけられると、社員たちは答えをもらうことが許されなくなり、自分の頭で解決策を考えなければならなくなるのです。
さらに、このマネージャーは「問いの後に60秒間黙る」というルールを追加しました。これにより、現場の社員たちは頭をフル回転させ、自ら答えを出そうとします。
その結果、どうなったと思いますか? 現場は自ら考える人材で溢れるようになり、成果も鰻登りに向上していったのです。
この成功の鍵は、良い問いを立てるだけでなく、「相手の答えが出るのを待つ」という姿勢にあったと著者は語っています。
まとめ:問いを立て、答えを待つ力を身につけよう
いかがでしたでしょうか? 「なぜ?」と責めるような悪い問いではなく、現状と望ましい目標のギャップを明確にする「良い問い」を立てることが、問題解決の第一歩です。そして、目標を考える際は、手段と混同しないように注意しましょう。
さらに、良い問いを立てたら、焦らずに相手が自ら答えを見つけるのを「待つ」ことが、成果を最大化する秘訣です。
皆さんもぜひ、日々の生活や仕事の中で、現状と理想の状態を整理し、「どういう状態になったら良いのだろう?」という問いを立て、それに自分なりの答えを見つける練習をしてみてください。この「問いの力」が、正解のない時代を生き抜くあなたの大きな武器となるはずです。
参考資料
【いまあなたに必要なのは答えじゃない。問いの力だ。】:https://amzn.to/4eYyOwD
👉【いまあなたに必要なのは答えじゃない。問いの力だ。】:https://amzn.to/4eYyOwD