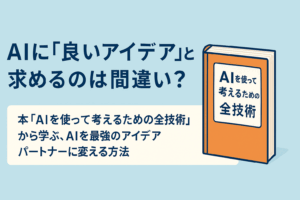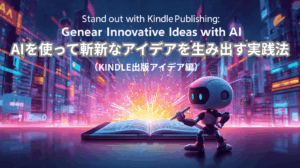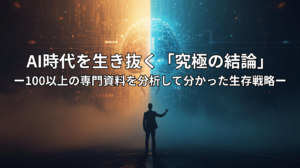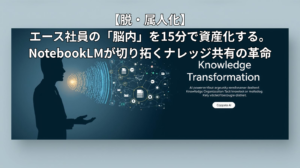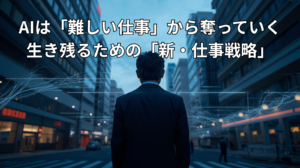みなさんはAIに質問して「なんだか普通の答えしか返ってこなかったな」と感じたことはありませんか?
「AIは人間の仕事を奪う」とニュースで聞く一方、いざChatGPTなどを使ってみると、無難な答えばかりで拍子抜け…そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
今回ご紹介する書籍『AIを使って考えるための全技術』は、そうした“AIにがっかりする”体験を逆手に取り、AIを「最強のアイデアパートナー」として活用するための方法を教えてくれる一冊です。特に印象的だったポイントをまとめてみました。
多くの人がしているAIへの誤解
多くの人は「AIにすごいアイデアを考えてもらえる」と期待します。ですが、著者はそれを真っ向から否定します。
なぜなら、良いアイデアというのは 「新しさ × 役立つこと」 の掛け算からしか生まれないからです。AIは学習した情報をもとに回答を作り出しますが、そのままではありきたりな答えになりがち。だから「AIが大したことない」と感じてしまうのです。
AIの本当の役割は「アイデアの量産」
本当に注目すべきは、AIが持つ “量産能力”。
人間は短時間で大量のアイデアを出そうとすると、どうしても疲れてしまい、途中で手が止まります。しかしAIは違います。どれだけでもアイデアを出し続けられる。
つまりAIの役割は「質の高い答えを出すこと」ではなく、「私たちが思いもよらないアイデアの種を大量に提示してくれること」にあるのです。
人間とAIの“ずるい役割分担”
AIがアイデアを大量に生み出し、人間はその中から面白そうなものを選び、育てていく。これが本書で語られる“ずるい役割分担”です。
AIが出してくれるのは玉石混交のアイデアですが、その中には必ず光る種が隠れています。その種を見つけ、自分の経験や視点を掛け合わせることで、唯一無二のアイデアへと育てることができます。
実践テクニック:エクスカーション法
本書で紹介される具体的な方法の一つが 「多様な特徴(エクスカーション法)」 です。
やり方はとてもシンプル。AIに対して「まったく異なる特徴を持つものをいくつか挙げて」と依頼し、それぞれから連想されるキーワードを抽出。最後にそれらを組み合わせて新しいアイデアを作ります。
例として著者は「新しいYouTubeチャンネルの企画」をテーマに実験しました。
- カメレオンワークス:カメレオンの順応性と生物の省エネを組み合わせ、現代社会をしなやかに生き抜くためのライフハックを紹介するチャンネル。
- 夜の森のフクロウ書斎:フクロウとキノコが登場し、自然の知恵をもとに世界を語るユニークな企画。
- サメ式トレンド判定:サメの嗅覚とタコの柔軟性をヒントに、次に来るビジネストレンドを解説するチャンネル。
一見突飛なアイデアでも、視点を変えるきっかけになります。
アイデアを“自分ごと化”する工夫
AIが出したアイデアをそのまま読むだけでは「他人の考え」と感じてしまい、やる気が続かないことがあります。これは心理学で 「NIH症候群(Not Invented Here)」 と呼ばれる現象。
そこで大切なのが、 AIのアイデアを自分のものにするプロセス です。AIが出した複数の案から面白いと思うものを選び、手を加え、磨き上げていく。その瞬間、アイデアは“自分の子ども”のように愛着が湧き、自然と実行に移したくなるのです。
他分野への応用も可能
本書ではYouTube企画を例に解説していますが、応用範囲は無限大です。
- 新商品の開発
- マーケティング戦略の立案
- スポーツや教育での戦術アイデア
- 日常の生活改善や自己成長のヒント
- KINDLE出版企画
どんなテーマでも、AIは膨大なアイデアを提供してくれます。そして、私たちはその中から“使える種”を育てることで、成果に結びつけることができます。
まとめ
『AIを使って考えるための全技術』から学べることは明快です。
- AIに求めるのは「質」ではなく「量」
- 多様な特徴(エクスカーション法)で発想を広げる
- AIのアイデアを“自分ごと化”して育てる
AIは魔法の答えをくれる存在ではありません。けれど、発想の種を無限に生み出し続けるパートナーとしては最強のツールです。AIを上手に“準備役”として使い、自分のクリエイティビティを引き出してみませんか。
👉 参考書籍:『AIを使って考えるための全技術』
👉今回で紹介した「魔法のプロンプト」
まず、特徴が異なる動物や生物を10個あげてください。 次にその動物から連想できる特徴や機能を各10個あげてください。 最後に、連想した単語と組み合わせて有益な【】の案を10個考えてください。👉コピペして【】の中身をあなたのテーマに変えるだけで使えます
参考図書
今回解説した内容は、書籍『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている50以上のテクニックのうちの1つです。もっとずるい思考法を知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
技法1:多様な視点でアイデアうを生み出す『多様な特徴』(「動物・生物」が持つ機能や特徴をヒントにして、アイデアを発想。