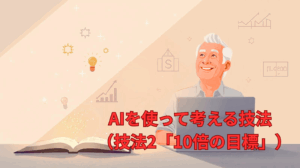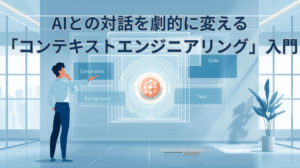「何か面白いアイデアはない?」
会議中、突然そう振られて頭が真っ白になった経験はありませんか?周りが次々と意見を出す中で、自分だけ何も思いつかず、冷や汗が流れる気まずい時間。
「アイデアを出すのが得意な同僚は、きっと生まれ持った才能があるんだろうな…」
そう諦めてしまった方もいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。創造力や発想力は、一部の天才だけが持つ特別な才能ではありません。それは、正しいトレーニングで誰でも鍛えられる「思考の筋肉」なのです。
この記事では、AIを相棒に、あなたの「思考の筋肉」を劇的に鍛え、凡人でも天才的なアイデアを次々と生み出すための科学的かつ具体的な方法をご紹介します。
アイデアの源泉は「無関係なものの結合」にあった
そもそも、革新的なアイデアはどこから生まれるのでしょうか?
ブレインストーミングの生みの親として知られるアレックス・オズボーンは、著書の中で興味深い逸話を紹介しています。ある飾り付け職人は、アイデアに行き詰まると、様々な単語や雑誌の切り抜きが入った袋に手を入れ、ランダムに取り出した一つと部屋の装飾を「無理やり結びつけて」デザインを決めていたというのです。
この逸話が示すのは、創造性の世界における一つの真実です。それは、「一見、全く無関係なもの同士を結びつけると、革新的なアイデアにつながりやすい」ということ。
この考え方は、1962年に心理学者サーノフ・メドニックが発表した伝説的な論文によっても裏付けられています。彼は論文の中で、創造性を「互いに離れたアイデアを結びつけて、新しい組み合わせを作る能力」と定義しました。つまり、全く関係ないアイデアAとアイデアBを結びつける能力が高い人ほど、創造性が高いということです。
しかし、この「無関係な単語を見つけ、課題と強制的に結びつける」という作業は、人間がやろうとすると非常に骨が折れます。
そこで登場するのがAIです。この創造性の核心でありながら面倒な作業を、AIに全て自動でやらせてしまおうというのが、今回ご紹介するテクニックの核心です。
【実践】AIを使って「稼げる副業アイデア」を考えてみた
それでは、実際にAIを使ってアイデア発想を実践してみましょう。今回は多くの人が関心を持つであろう「手軽に始められて、ちゃんと稼げる副業のアイデア」というお題で試してみます。
Step1: AIに「無関係な単語」を大量生成させる
まずは、アイデアの元となる「無関係な単語」をAIにリストアップさせます。今回はChatGPT(GPT-4o)に以下のプロンプトを投げました。
【プロンプト】
日本語の単語を100個列挙してください。単語の感覚はスラッシュで区切ってください。その後、そこからランダムに単語を選び、「手軽に始められる副業のアイデア」というお題と組み合わせて、魅力的なアイデアを3つ考えてください。
AIはまず、「空/猫/本/音楽/旅/…」といった単語を100個生成しました。そして、その中からランダムに選んだ単語を組み合わせ、次のようなアイデアを提案してくれました。
- 【記憶 × 料理】思い出の味、再現しますサービス
依頼者の「子供の頃に母が作ってくれた料理」「旅行先で食べた忘れられない一品」などのエピソードを元に、思い出の味を再現する。 - 【料理 × 声】声で届けるお料理ラジオ
心地よい声で料理の手順やコツを配信する音声サービス。「レシピサイトは手が汚れてスマホを操作しにくい」という悩みを解決する。 - 【記憶 × 声】あなたの人生、短編ボイスドラマ化サービス
依頼者の人生の大切な記憶を元に脚本を書き、ボイスドラマを制作する。
いかがでしょうか。悪くはないですが、どこか「ありきたり」で、すでに存在しそうなサービスですよね。
Step2: 「意外な単語」を指定して、アイデアの斬新さを引き上げる
もっと斬新なアイデアが欲しい。そのためには、副業というテーマから、より遠い、意外性のある単語をぶつけることが効果的です。
そこで、生成されたリストの中から、あえて「怒り」「破壊」「孤独」というネガティブで副業とは結びつかなそうな単語を選び、追加で指示を出します。
【追加プロンプト】
「怒り」「破壊」「孤独」という単語を組み合わせて、斬新な副業アイデアを5つ考えてください。
すると、AIの回答は劇的に変わりました。
- アンガー・デストラクション・ルーム
個室で心ゆくまでモノを破壊できるストレス発散サービス。 - 廃墟再生アートプロジェクト
取り壊しが決まった廃ビルを舞台にした参加型の破壊アート。 - 感情浄化スマホゲーム「インナービースト」
プレイヤーの怒りや孤独をエネルギー源に怪物を育て、仮想空間を破壊するゲーム。 - 体感型一人芝居「破壊セラピスト」
セラピストが観客(クライアント)の怒りを引き出し、目の前で物を破壊することで感情を代弁・昇華させる演劇。 - 音楽アルバム「ノイズ・ミュージック」
孤独・怒り・破壊の3部構成で人間の内面を描くコンセプトアルバム。
かなり斬新で面白そうなアイデアが出てきました。しかし、今度は「手軽に始められる」という当初の条件から外れてしまいました。
Step3: 条件を加えて、アイデアを現実的にする
そこで、最後の仕上げです。斬新さを保ちつつ、実現可能性を高めるために、再度条件を追加します。
【最後のプロンプト】
先ほどの5つのアイデアを元に、もっと手軽に始められる副業アイデアを5つ考えてください。
この指示によって、ようやく現実的でユニークなアイデアにたどり着きました。
- あなたの代わりに“知的”な悪口を考えますサービス
日常の怒りやモヤモヤを、ユーモアや皮肉に富んだ文章に変換して提供する。 - 常識破壊チャンネル
世の中の「当たり前」に疑問を投げかけるコンテンツを配信。 - 黒歴史クリーナー
過去のSNS投稿などのデジタルデータを削除代行・コンサルティングする。 - 退屈な日常を破壊する「今日の裏ミッション」
LINEなどを通じて、日常のルーティンを破壊するような突拍子もない指令を毎日配信するサブスクサービス。
このように、AIと対話を重ねることで、ありきたりなアイデアから、斬新で、かつ実現可能なアイデアへと進化させることができたのです。
警告:AIは思考の「きっかけ」。全てを任せるのは危険
ここで一つ、非常に重要な注意点があります。それは、「全てをAIに任せるのは危険だ」ということです。
AIの出力は、あくまで思考の「きっかけ」や「たたき台」に過ぎません。AIが出した答えをそのまま使うのではなく、そこから人間が介入し、AIと対話しながらアイデアを洗練させていくプロセスこそが最も重要です。
例えば、AIが生成した単語リストを眺めて、あなたの直感が「香り」という単語にピクリと反応したとします。そしたら、今度はあなたから「この“香り”を使って何か面白い副業は作れないか?」とAIに問いを投げ返すのです。
このAIとの対話のキャッチボールを重ねることで、アイデアは単なるAIの提案ではなく、あなた自身の血の通ったオリジナルなものへと磨き上げられていきます。
AI格差時代の到来。あなたは未来を切り拓く側になる
かつては一部の熟練クリエイターだけが長年の経験で体得していた「意外なもの同士を結びつける」という強力な思考法。今や、AIとプロンプトさえあれば、誰もがいつでも好きなだけ使えるようになりました。
しかし、これは同時に恐ろしい時代の幕開けでもあります。この魔法のような使い方を「知っているか、知らないか」「使うか、使わないか」。たったそれだけの違いが、気づかないうちに、人と人の能力の間に絶望的なまでの差を生み出してしまうのです。
半年後、1年後、AIを使いこなす同僚やライバルは、あなたからはもう見えない、はるか先へ進んでいるかもしれません。
あなたには、どうか時代の変化を傍観する側ではなく、自らの手で未来を切り拓いていく側でいてほしい。それが私の何よりの願いです。
【本日のまとめ】
- 創造性の源泉は「遠いもの同士を結びつける」こと。
- AIにランダムな単語生成と結合を任せ、思考のきっかけを掴む。
- AIの出力はあくまで起点。人間が介入し対話を深めることでアイデアは磨かれる。
さあ、あなたが今行き詰まっているその課題に、AIを使って全く無関係な言葉をぶつけてみてはいかがでしょうか?きっと、想像もしなかった化学反応が起こるはずです。
参考プロンプト(技法9:ランダムな単語)
まず、日本語の単語を100個列挙してください。単語の間は「/」で区切ってください。その出力の後、次に、そこからランダムに単語を選び「お題」と組み合わせて魅力的なアイデアを考えてください。「お題」は〈 ここにアイデアを得たい対象を記入 〉です。
参考書籍
この動画で解説した内容は、書籍『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている50以上のテクニックのうちの1つです。もっとずるい思考法を知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
👉『AIを使って考えるための全技術』